「顧客志向を当たり前に」AI接客プラットホームのPdMを募集

時給 4,000円 ~ 5,500円
雇用形態: 副業転職(業務委託から正社員)
勤務地:
CakePHP
の転職・求人情報
1~20件(217件)

時給 4,000円 ~ 5,500円
雇用形態: 副業転職(業務委託から正社員)
勤務地:

年収 450万円 ~ 600万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 700万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 800万円 ~ 1,000万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 550万円 ~ 850万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 800万円
雇用形態: 副業転職(業務委託から正社員)
勤務地:

年収 400万円 ~ 600万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 600万円 ~ 900万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 800万円 ~ 1,200万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 700万円 ~ 1,000万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 900万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 900万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 900万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 800万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 800万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 264万円 ~ 500万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

時給 1,500円 ~ 3,000円
雇用形態: 業務委託
勤務地:

時給 4,000円 ~ 8,000円
雇用形態: 業務委託
勤務地:

時給 2,500円 ~ 6,500円
雇用形態: 業務委託
勤務地:

時給 2,500円 ~ 6,500円
雇用形態: 業務委託
勤務地:

エージェント
転職をお考えの方は
エンジニア / PM
デザイナー / データ分析
の経験のあるエージェントにお任せください
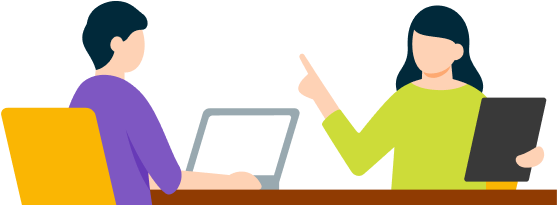
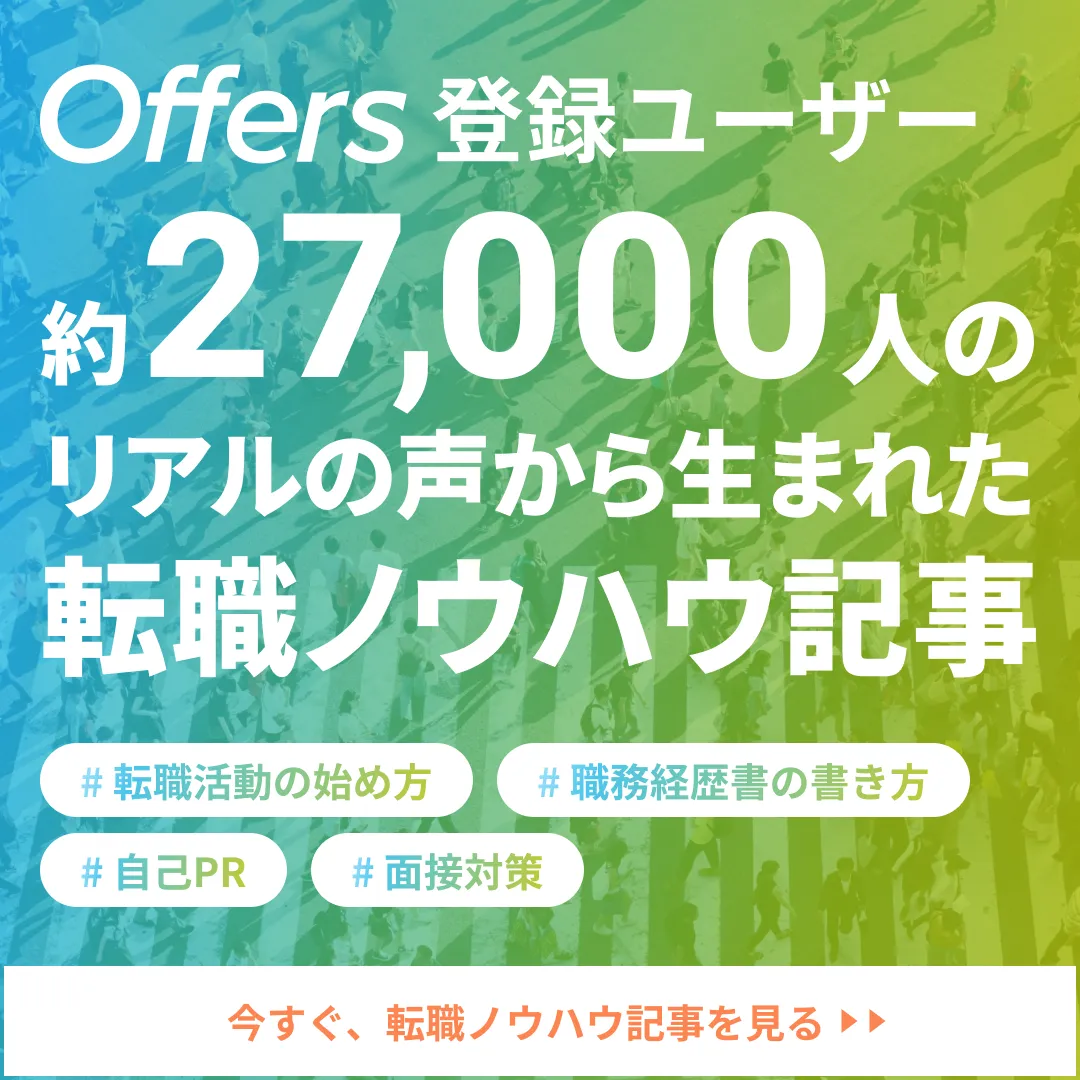
アカウントを作成して、求人情報のブックマークや応募の管理ができます。
求人に関するサマリ
CakePHPは、ウェブアプリケーション開発を効率化するためのPHPフレームワークです。2005年に登場して以来、多くの開発者に愛用されてきました。このフレームワークの特徴は、「規約よりも設定」という理念に基づいていることです。つまり、開発者が細かな設定に時間を取られることなく、アプリケーションのロジックに集中できるようになっているのです。
CakePHPの基本的な構造は、Model-View-Controller(MVC)アーキテクチャに基づいています。これにより、アプリケーションのデータ処理、表示、制御を明確に分離し、保守性の高いコードを書くことができます。また、データベース抽象化レイヤーやセキュリティ機能など、現代のウェブアプリケーション開発に必要な機能が豊富に用意されています。
初心者にも扱いやすく、経験豊富な開発者にとっても生産性の高いツールとして知られているCakePHPは、様々な規模のプロジェクトで活用されています。セキュリティ面でも優れており、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの脆弱性に対する防御機能が標準で組み込まれています。
CakePHPは、その柔軟性と堅牢性から、様々な業界で幅広く利用されています。例えば、eコマースプラットフォームの構築や、企業の内部管理システム、さらにはソーシャルネットワークサービスの開発にも活用されています。
具体的な例を挙げると、イギリスの大手スーパーマーケットチェーンTescoは、自社のオンラインショッピングプラットフォームの一部にCakePHPを採用しています。また、アメリカの教育技術企業Blackboardも、学習管理システムの開発にCakePHPを利用しているのです。
日本国内でも、CakePHPの採用事例は増加傾向にあります。大手企業から中小企業まで、業務効率化や顧客サービス向上のためのウェブアプリケーション開発にCakePHPが選ばれています。この背景には、日本語のドキュメントが充実していることや、国内のコミュニティが活発であることも影響しているでしょう。
CakePHPの中核を成す特徴の一つが、Model-View-Controller(MVC)アーキテクチャです。このアーキテクチャは、アプリケーションを3つの主要な部分に分割することで、コードの管理と保守を容易にします。各部分の役割は明確に定義されており、開発者はこの構造に従ってコードを書くことで、整理された、理解しやすいアプリケーションを作ることができるのです。
Modelは、データベースとの対話やビジネスロジックを担当します。例えば、ユーザー情報の取得や更新、注文処理などがModelの役割です。Viewは、ユーザーに表示される部分を担当し、HTMLやCSSを使って情報を整形します。Controllerは、ModelとViewの橋渡し役として機能し、ユーザーからのリクエストを適切に処理し、必要なデータをModelから取得してViewに渡す役割を果たします。
このMVCアーキテクチャにより、CakePHPでは各機能が明確に分離され、コードの再利用性が高まります。また、複数の開発者が同時に異なる部分を作業することも容易になり、大規模プロジェクトでの開発効率が向上するのです。実際、多くの開発者がこのアーキテクチャの採用により、プロジェクトの見通しが良くなったと報告しています。
CakePHPの特筆すべき機能の一つに、「bake」があります。この機能は、コマンドラインインターフェース(CLI)を通じて、アプリケーションの基本的な構造やコードを自動生成するツールです。bake機能を使用することで、開発者は短時間で基本的なCRUD(Create, Read, Update, Delete)操作を持つアプリケーションの骨格を作り上げることができます。
具体的には、bake機能を使うと、データベーステーブルの構造に基づいて、対応するModel、View、Controllerのファイルを自動的に生成できます。これにより、開発の初期段階での作業時間を大幅に短縮することが可能になります。また、生成されたコードは、CakePHPの規約に則ったものになるため、初心者でもフレームワークの基本的な使い方を学ぶ良い機会にもなるのです。
bake機能の利用により、プロジェクトの立ち上げ時間を平均で30%以上短縮できるという報告もあります。ただし、自動生成されたコードはあくまでも基本的な機能のみを提供するものであり、実際のアプリケーションに必要な細かい機能やカスタマイズは、開発者自身が行う必要があることを忘れてはいけません。
CakePHPの大きな強みの一つに、活発なコミュニティとサポート体制があります。世界中の開発者がCakePHPを使用し、その経験や知識を共有しています。この強力なコミュニティは、新しい開発者の学習を助け、経験豊富な開発者にとっても問題解決の場となっているのです。
公式フォーラムやStack Overflowなどのプラットフォームでは、CakePHPに関する質問や議論が日々活発に行われています。また、GitHubでのイシュートラッキングを通じて、バグ報告や機能要望も直接開発チームに届けることができます。これにより、フレームワークの品質向上と進化が継続的に行われているのです。
さらに、CakePHPは定期的にアップデートされており、新しい機能の追加やセキュリティの強化が行われています。例えば、2023年にリリースされたCakePHP 4.4では、PHP 8.2のサポートが追加され、パフォーマンスの向上も図られました。このような継続的な改善により、CakePHPは常に最新の技術トレンドに対応し、開発者のニーズに応え続けているのです。
CakePHPには数多くの利点がありますが、その中でも特に重要なものをいくつか挙げてみましょう。まず、学習曲線が比較的緩やかであることが挙げられます。「規約よりも設定」の原則に基づいているため、初心者でも短期間でアプリケーション開発を始められるのです。実際、多くの開発者が、他のフレームワークと比べてCakePHPの習得が容易だったと報告しています。
次に、生産性の高さが大きな利点です。先ほど触れたbake機能や、豊富な組み込みヘルパー、プラグインシステムにより、開発速度を大幅に向上させることができます。ある調査によると、CakePHPを使用することで、プロジェクトの開発時間を平均で40%削減できたという結果も出ています。
セキュリティ面での強さも、CakePHPの重要な利点の一つです。クロスサイトスクリプティング(XSS)やSQLインジェクションなどの一般的な攻撃に対する防御機能が標準で組み込まれており、開発者が意識せずともある程度のセキュリティが確保されます。これにより、セキュリティに関する知識が十分でない開発者でも、比較的安全なアプリケーションを構築できるのです。
一方で、CakePHPにも欠点や課題はあります。その一つが、大規模なアプリケーションでのパフォーマンスです。CakePHPは小中規模のプロジェクトでは優れた性能を発揮しますが、非常に大規模なアプリケーションや高負荷な環境では、他のフレームワークと比べて若干のパフォーマンス低下が見られることがあります。
また、柔軟性という観点では、他のフレームワークに劣る面があります。CakePHPの「規約よりも設定」という原則は、多くの場合で開発を容易にしますが、逆に特殊な要件や独自の構造を持つプロジェクトでは制約になることもあります。例えば、データベース設計に厳格な命名規則があるため、既存のデータベースとの統合が難しい場合があるのです。
さらに、バージョンアップ時の互換性の問題も指摘されています。特に、メジャーバージョンアップ(例:3.xから4.xへの移行)の際には、大幅な変更が加えられることがあり、既存のアプリケーションの移行に多大な労力が必要になる場合があります。これは、長期的なプロジェクト管理において考慮すべき重要な点となっています。
CakePHPとLaravelは、どちらもPHPフレームワークとして人気がありますが、いくつかの重要な違いがあります。まず、学習曲線に関しては、CakePHPの方が比較的緩やかだと言えるでしょう。CakePHPは「規約よりも設定」の原則に基づいているため、初心者にとっては取っ付きやすい面があります。一方、Laravelはより柔軟で強力な機能を持っていますが、その分、習得に時間がかかる傾向があります。
パフォーマンスの面では、一般的にLaravelの方が優れているとされています。特に大規模なアプリケーションや高負荷な環境下では、Laravelの方が効率的に動作する傾向があります。ただし、小中規模のプロジェクトでは、CakePHPも十分な性能を発揮します。実際、ある比較調査では、中規模のeコマースサイトでCakePHPとLaravelのパフォーマンスを測定したところ、ページロード時間に5%程度の差しかなかったという結果も出ています。
コミュニティとエコシステムの観点では、現在はLaravelの方が優位に立っています。Laravelは多くの開発者に支持され、豊富なパッケージやツールが提供されています。一方、CakePHPも安定したコミュニティを持っていますが、規模や活発さではLaravelには及びません。ただし、CakePHPは日本語のドキュメントが充実しているため、日本国内での採用には有利な面もあるのです。
CakePHPとSymfonyは、どちらもMVCアーキテクチャを採用していますが、アプローチに違いがあります。CakePHPが「規約よりも設定」を重視しているのに対し、Symfonyはより柔軟な設定オプションを提供しています。このため、Symfonyは大規模で複雑なプロジェクトに適していると言われています。
学習曲線に関しては、CakePHPの方が緩やかです。Symfonyは非常に強力ですが、その分複雑さも増すため、習得には時間がかかります。ある調査によると、PHPの経験がある開発者が基本的な機能を使いこなせるようになるまでの期間は、CakePHPが平均2週間程度なのに対し、Symfonyでは1ヶ月以上かかるケースが多いという結果が出ています。
パフォーマンスの面では、Symfonyが優位に立つことが多いです。特に、大規模なエンタープライズアプリケーションでは、Symfonyの方が効率的に動作する傾向があります。ただし、中小規模のプロジェクトでは、CakePHPも十分な性能を発揮します。実際、ある中規模のCMSプロジェクトでの比較では、CakePHPとSymfonyのレスポンス時間の差は10%以内に収まったという報告もあります。
CakePHPとCodeIgniterは、どちらも軽量で高速なPHPフレームワークとして知られています。しかし、その設計思想や機能セットには違いがあります。CodeIgniterは極めて軽量で、最小限の設定で動作することを特徴としています。一方、CakePHPはより多くの機能を標準で提供し、規約に基づいた開発を促進します。
パフォーマンスの面では、CodeIgniterが若干優位に立つことが多いです。特に、小規模なプロジェクトや高速なレスポンスが求められる場面では、CodeIgniterの軽量さが活きてきます。ある比較テストでは、同じ機能を持つ簡単なアプリケーションで、CodeIgniterはCakePHPより約15%速いレスポンス時間を記録したという結果もあります。
しかし、機能の豊富さや拡張性という点では、CakePHPの方が優れています。CakePHPは、データベース抽象化、セキュリティ機能、認証システムなど、多くの機能を標準で提供しています。これにより、開発者は基本的な機能の実装に時間を取られることなく、アプリケーション固有のロジックに集中できるのです。
CakePHPは、様々な業界の企業で幅広く採用されています。例えば、大手eコマース企業のZapposは、自社のバックエンドシステムの一部にCakePHPを使用しています。Zapposの開発者によると、CakePHPの採用により、新機能の開発速度が約25%向上し、コードの保守性も大幅に改善されたとのことです。
また、教育分野では、オンライン学習プラットフォームを提供するUdemyが、管理システムの一部にCakePHPを採用しています。Udemyの技術チームは、CakePHPの柔軟性と拡張性が、急速に成長する事業のニーズに対応する上で非常に有効だったと報告しています。実際、CakePHP導入後の1年間で、システムの安定性が15%向上し、新機能のリリース頻度が2倍になったというデータもあります。
日本国内では、大手人材紹介会社のリクルートキャリアが、自社の求人情報管理システムにCakePHPを採用しています。リクルートキャリアの開発者によると、CakePHPの採用により、システムの開発期間が従来の手法と比べて約30%短縮され、さらにコードの再利用性が高まったことで、長期的な保守コストの削減にもつながっているそうです。
CakePHPを使用したプロジェクト管理では、アジャイル開発手法が多く採用されています。特に、スクラムやカンバンといった手法との相性が良いとされています。CakePHPの機能的な特徴が、これらの開発手法と上手く噛み合うためです。
例えば、CakePHPのbake機能を活用することで、スプリントごとの基本的な機能実装を迅速に行うことができます。ある調査によると、bake機能を効果的に使用したチームは、スプリントの目標達成率が平均で20%向上したという結果が出ています。また、MVCアーキテクチャに基づいた明確な構造により、チームメンバー間でのコード理解が容易になり、コードレビューの効率も上がります。
さらに、CakePHPのプラグインシステムを活用することで、機能の追加や変更を柔軟に行えます。これにより、顧客の要求変更にも迅速に対応できるのです。実際、ある中規模のWeb開発プロジェクトでは、CakePHPのプラグインシステムを活用することで、機能追加にかかる時間を平均で40%削減できたという報告もあります。
CakePHPの学習において、最も重要なリソースの一つが公式ドキュメントです。CakePHPの公式ウェブサイトで提供されているこのドキュメントは、フレームワークの基本的な概念から高度な機能まで、幅広くカバーしています。特筆すべきは、日本語を含む多言語対応がなされていることです。これにより、英語が苦手な開発者でも、母国語でCakePHPを学ぶことができます。
公式ドキュメントは、初心者向けのチュートリアルから始まり、各コンポーネントの詳細な説明、さらにはベストプラクティスやトラブルシューティングガイドまで、幅広い内容を網羅しています。特に、「クイックスタートガイド」は、CakePHPを使い始める開発者にとって非常に有用です。このガイドを通じて、多くの開発者が数時間でCakePHPの基本を理解し、簡単なアプリケーションを作成できるようになったと報告されています。
また、公式ドキュメントは定期的に更新されており、最新のバージョンに対応した情報を常に提供しています。例えば、新しいメジャーバージョンがリリースされる際には、バージョン間の変更点や移行ガイドも詳細に記載されます。これにより、開発者は常に最新の情報にアクセスし、効率的に学習や開発を進めることができるのです。
CakePHPの学習をさらに深めたい開発者にとって、オンラインコースは非常に有効なリソースとなります。Udemy、Coursera、edXといった主要なオンライン学習プラットフォームでは、CakePHPに特化したコースが複数提供されています。これらのコースは、初心者から上級者まで、様々なレベルの開発者に対応しています。
例えば、Udemyで人気の「CakePHP 4 - The Complete Guide」というコースでは、CakePHPの基礎から応用まで、実践的なプロジェクトを通じて学ぶことができます。このコースを受講した開発者の多くが、8週間程度でCakePHPを使った実用的なアプリケーションを開発できるようになったと報告しています。また、Courseraの「Web Application Development with PHP and CakePHP」というコースでは、より高度なトピックについても学ぶことができ、既存のPHP開発者のスキルアップに役立っています。
これらのオンラインコースの大きな利点は、自分のペースで学習を進められることです。また、多くのコースで実践的な課題やプロジェクトが用意されており、理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができます。実際、あるサーベイによると、オンラインコースを通じてCakePHPを学んだ開発者の90%以上が、学習後6ヶ月以内に実際のプロジェクトでCakePHPを使用し始めたという結果が出ています。
CakePHPの学習において、書籍も重要な役割を果たします。多くの専門書が出版されており、初心者から上級者まで、様々なレベルの開発者のニーズに応えています。例えば、「CakePHP 4 Application Development」という書籍は、CakePHP 4の基本から高度な機能まで網羅的に解説しており、多くの開発者から高い評価を得ています。
日本語の書籍も充実しており、「はじめてのCakePHP」や「CakePHP実践入門」といった本が人気です。これらの書籍は、日本語での解説や日本特有の開発事情を考慮した内容となっており、日本人開発者にとって非常に有用です。実際、ある調査によると、これらの日本語書籍を使って学習した開発者の80%以上が、3ヶ月以内にCakePHPを使った実務プロジェクトに参加できるレベルに達したという結果が出ています。
また、CakePHPコミュニティによって作成された無料の電子書籍やPDFガイドも多数存在します。これらの資料は、特定のトピックに焦点を当てた深い解説や、最新のベストプラクティスを提供しており、既存の CakePHP 開発者のスキルアップに役立っています。例えば、「CakePHP Security Cookbook」という無料の電子書籍は、CakePHPでのセキュアな開発方法について詳細に解説しており、多くの開発者がこの資料を参考にセキュリティ対策を強化しています。
エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職採用サービス「Offers(オファーズ)」では、非公開求人を含む豊富なIT・Web業界の転職・副業情報を提供しています。高年収の求人・高時給の案件や最新技術スタックを扱う企業など、あなたのスキルを最大限に活かせるポジションが見つかります。専任のキャリアアドバイザーが、入社日調整や条件交渉をきめ細かくサポート。転職・正社員求人、副業・業務委託案件、募集をお探しの方はOffersまでご相談ください。閉じる
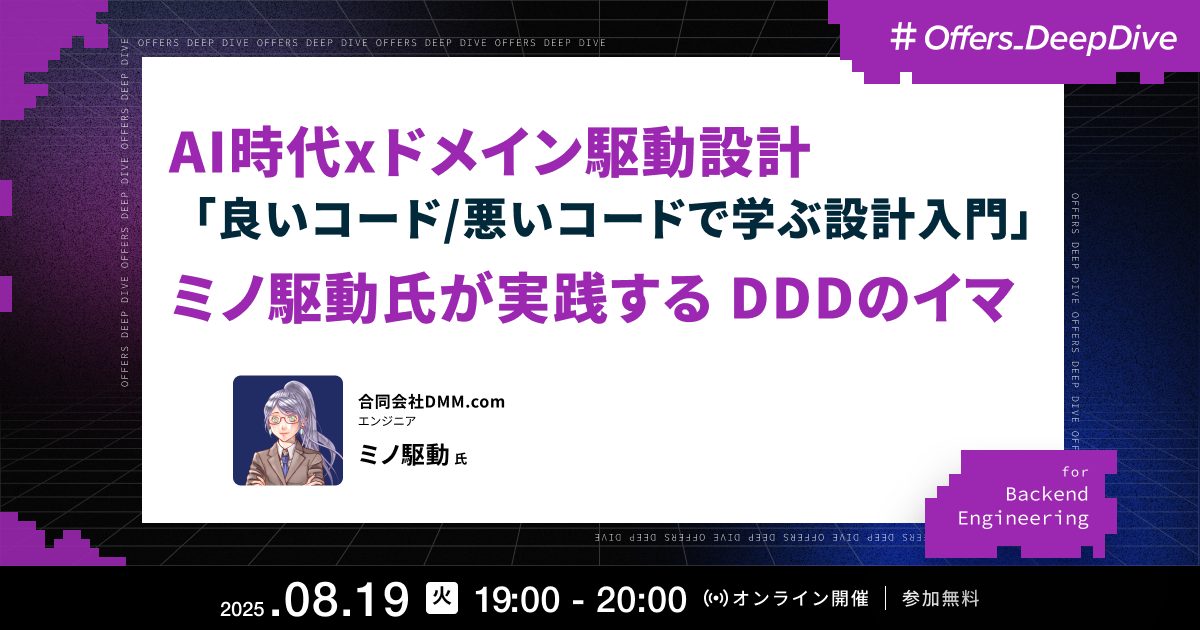
開催前
昨今、AIコーディングエージェントの進化と普及により、ソフトウェア開発はかつてないほど、加速しています。 さらにはコーディングだけでなく設計もAIに任せる場面も増え、「AI時代になれば、DDD(ドメイン駆動設計)のような手法はもう必要なくなるのでは?」そんな疑問を抱くエンジニアも多いのではないでしょうか。 今回のイベントでは、「良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門」のミノ駆動氏をお招きし、AI時代におけるDDDの在り方と新しい実践アプローチについて直接お話しいただきます。 AIによってDDDは不要になるのか、それとも在り方が変わるのか。ソフトウェア設計の第一線で活躍するミノ駆動氏が実践するDDDの在り方を伺うことで、今後の設計の在り方について理解する場になりましたら幸いです。
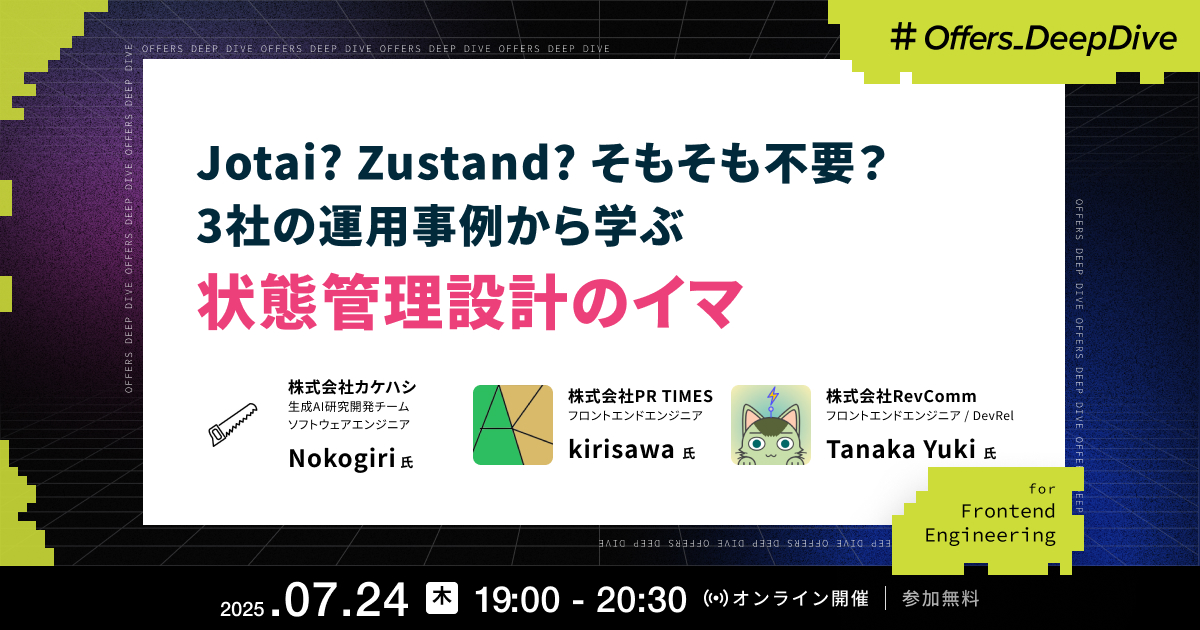
アーカイブ公開中
React開発において「状態管理」は避けて通れないテーマです。一方で「結局React標準のContext APIだけで十分?」「Recoilのメンテナンスが停止したけど次は?」「JotaiとZustandはどう違う?」といった疑問を抱えたまま、なんとなく導入を進めているケースも多いのではないでしょうか。 今回は、状態管理に関してJotai・Zustand・React標準のContext APIという異なるアプローチを取る3社をお招きし、実際の技術選定の背景や本番運用、移行の過程で得た知見を深掘りしていきます。 それぞれが採用・運用してきたライブラリのメリット・デメリットを共有しながら、各社の技術選定基準や設計方針、移行時の苦労と工夫まで、リアルな運用知見を語り合います。 「状態管理ライブラリ、今結局何を選ぶべき?」とモヤモヤを抱えている方や正解が見出せていない領域だと感じる方におすすめです。ぜひご参加ください。
開催日:
2025年7月24日(木)19:00~20:30
.jpg)
アーカイブ公開中
プロダクト開発の現場で「アクセシビリティ」という言葉を耳にする機会は、ここ数年で確実に増えています。一方でその多くは、「法律で求められているから」「顧客に言われたから」「上からの指示だから」といった受け身の対応にとどまっていることも少なくありません。 また、「高齢者や障害者向けの話で、自分たちには関係ない」「何をすればいいのか正直ピンとこない」と感じている方も多いのではないでしょうか。 そこで本イベントでは、デザイナーやエンジニアとしてアクセシビリティの分野で活躍するフリー株式会社 アクセシビリティスペシャリストの伊原力也氏、UIデザイナー兼フロントエンドエンジニアのymrl氏、株式会社 Helpfeel でエンジニアを務めるPasta-K氏という豪華メンバーをお招きし、そもそもなぜアクセシビリティが必要なのか、アクセシビリティは通常のプロダクト開発と比較した時に、どの程度の優先度なのか。本当にコストに見合うのか?といったリアルな疑問について伺います。 「アクセシビリティ」は自分にはまだ関係ないと思っている方、開発現場におけるリアルな取り組みを知りたい方、アクセシビリティの実装や設計に興味のある方、良いプロダクト開発を実現したいと考えている方にとって、有意義な対話の場となることを目指します。ぜひご参加ください! 🧑💻イベントでわかること アクセシビリティを実際にどの優先度で考えるべきなのかがわかる 建前でのアクセシビリティへの向き合い方ではなく、本音でどう向き合うべきかがわかる 自身の会社で本当にアクセシビリティを取り組む必要があるのか?という疑問がわかる
開催日:
2025年7月9日(水)19:00~20:30
.png)
アーカイブ公開中
昨今、AIコーディングエージェント(例:CursorやClineなど)の進化と普及により、ソフトウェア開発はかつてないほど、加速しています。 しかし同時に、PMから渡された仕様をエンジニアがそのままAIエージェントに読み込ませ、生成されたコードを使っただけでは、リリースに耐える品質を担保するのは難しいのが現実ではないでしょうか。 今回のイベントでは、AI駆動開発と実際に向き合ってきたPMのmiyattiさん、エンジニアのkagayaさんをお招きし、現場で直面しているAI駆動開発の限界や求められる品質基準について、それぞれの立場からお話しいただきます。 PMとエンジニア、両者の視点からAI駆動開発の“今”と“これから”を改めて考え直す貴重な機会です。AIを開発に取り入れている方、これから取り入れたいと考えている方、そして、PMとエンジニアの連携に課題意識を持っている方に、ぜひご参加いただきたい内容です。
開催日:
2025年6月24日(火)19:00~20:00
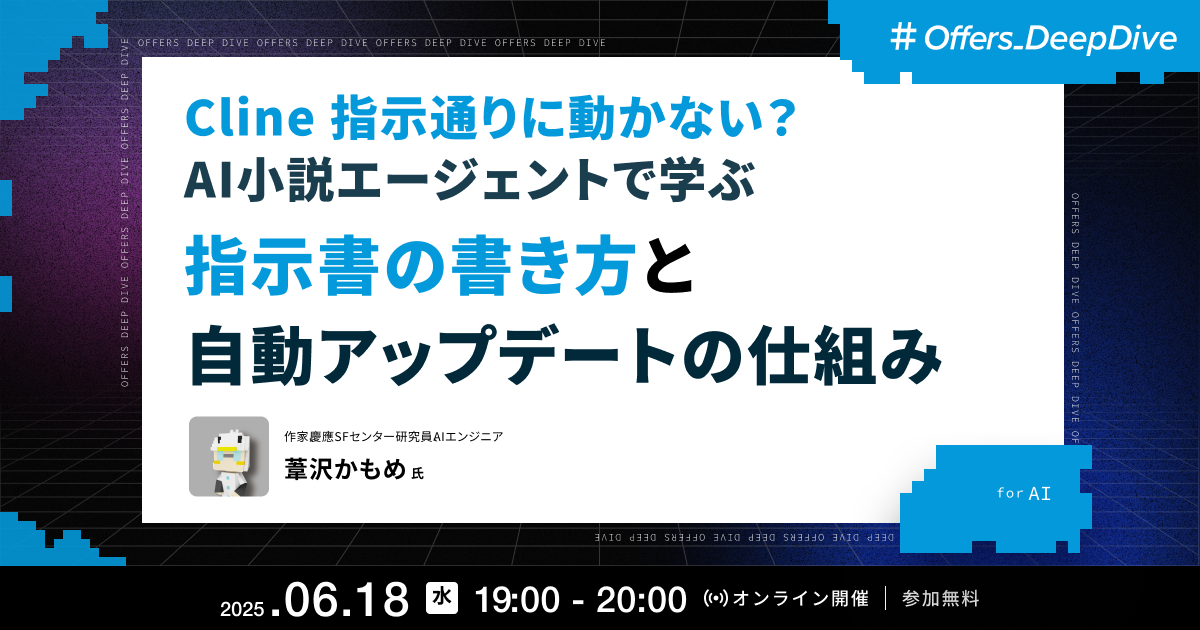
アーカイブ公開中
ClineやCursorなどの生成AIツールが急速に広がる中、「うまく動かない」「どこまで読み込ませるべきか分からない」そう感じることはありませんか? 本イベントでは、小説執筆という膨大な情報を扱う創作プロセスを題材に、下記のような、生成AIを意図通りに動かすための設計ノウハウを学べます。 - どういった情報をAIに読み込ませるべきかの切り分け - セッションをまたぐ長大なコンテキストを保持するための設計(Memory Bankの活用) - コードや文章を生成後に行うプロンプトの更新方法、およびその自動化 >※メモリバンクのURL: [https://docs.cline.bot/prompting/cline-memory-bank](https://docs.cline.bot/prompting/cline-memory-bank) Clineを中心に据えながらも、CursorやObsidianとの比較や、「そもそもAIに任せるべき部分・任せるべきでない部分はどこか?」という、今後の実務においても避けては通れない問いを扱う予定です。 Clineを導入しているものの、活用に課題を感じている方や、プロンプト設計に体系的な知見を持ちたい方にとって、有意義な学びの機会となる内容です。ぜひ、ご参加ください。
開催日:
2025年6月18日(水)19:00~20:00