2022年4月時点でクローズドテスト版を開発しており、並行してすでに弊社プロダクトに興味を持っている国内の素材系大企業約10社と対話を始めています。現在のチーム構成はフルタイムのメンバーはCEOとエンジニア2名、パートタイムのメンバーはエンジニア7名、UXデザイナー1名、材料科学者2名、BizDevが1名というチーム構成になっています。フルタイムのエンジニア2名を含めてアメリカ、アルゼンチン、中国出身のメンバーがおり、Day 1からインターナショナルな開発チームです。
- Slack + Notion+ Google Workspace + Zapier
- React.js + Next.js + Apollo Client + Xstate + Storybook +TypeScript
- Node.js + Python
- PostgreSQL + Hasura (GraphQL)+ Prisma
- Google Cloud Platform





.png)
.png)
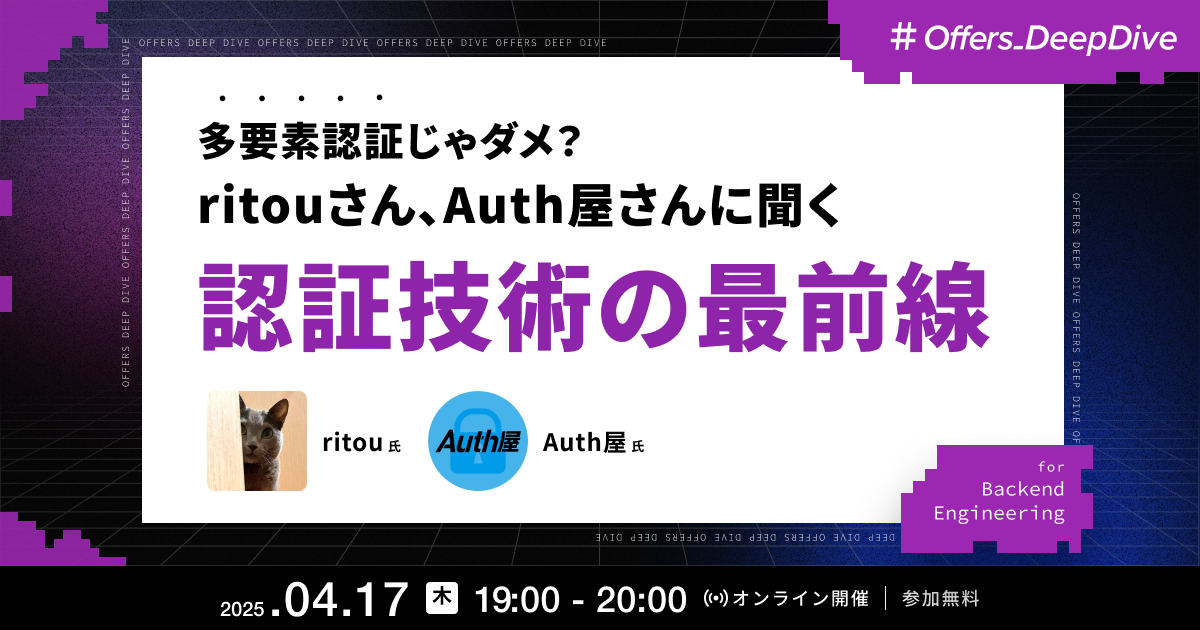
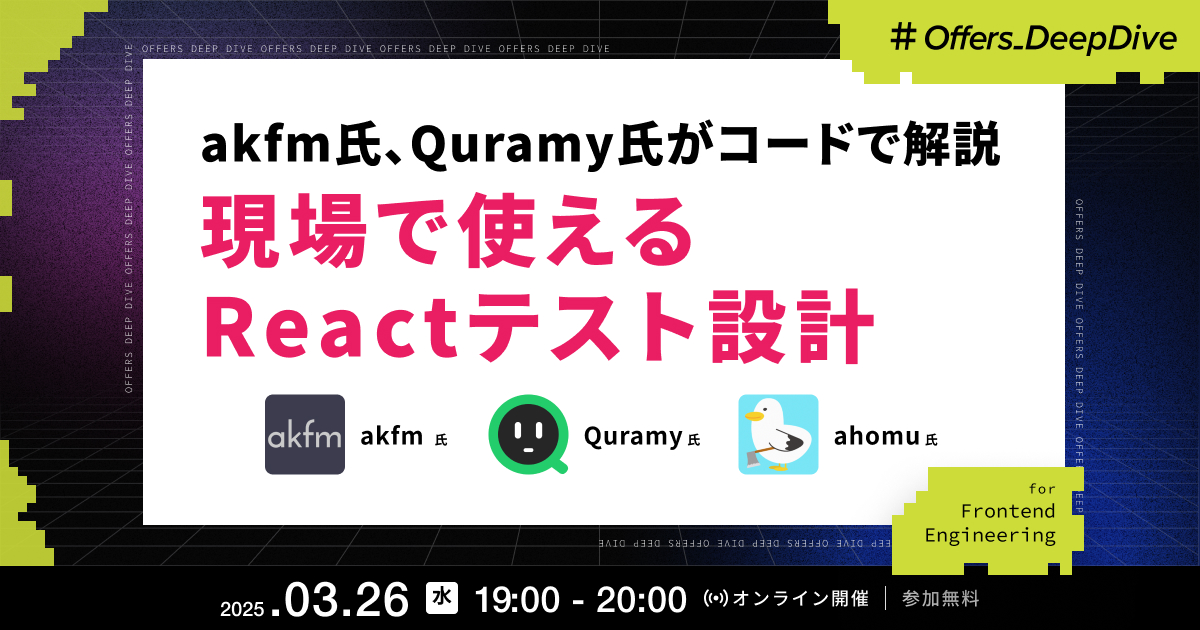
.png)