【副業スタート可】TROCCO プロダクトデザイナー/フルリモート可

時給 2,500円 ~ 5,000円
雇用形態: 副業転職(業務委託から正社員)
勤務地:
Slim
の転職・求人情報
1~5件(5件)

時給 2,500円 ~ 5,000円
雇用形態: 副業転職(業務委託から正社員)
勤務地:

年収 900万円 ~ 1,400万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 500万円 ~ 900万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

年収 400万円 ~ 600万円
雇用形態: 正社員
勤務地:

時給 2,500円 ~ 5,000円
雇用形態: 業務委託
勤務地:

エージェント
転職をお考えの方は
エンジニア / PM
デザイナー / データ分析
の経験のあるエージェントにお任せください
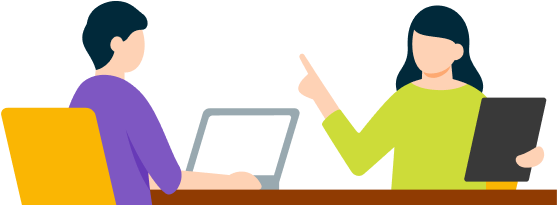
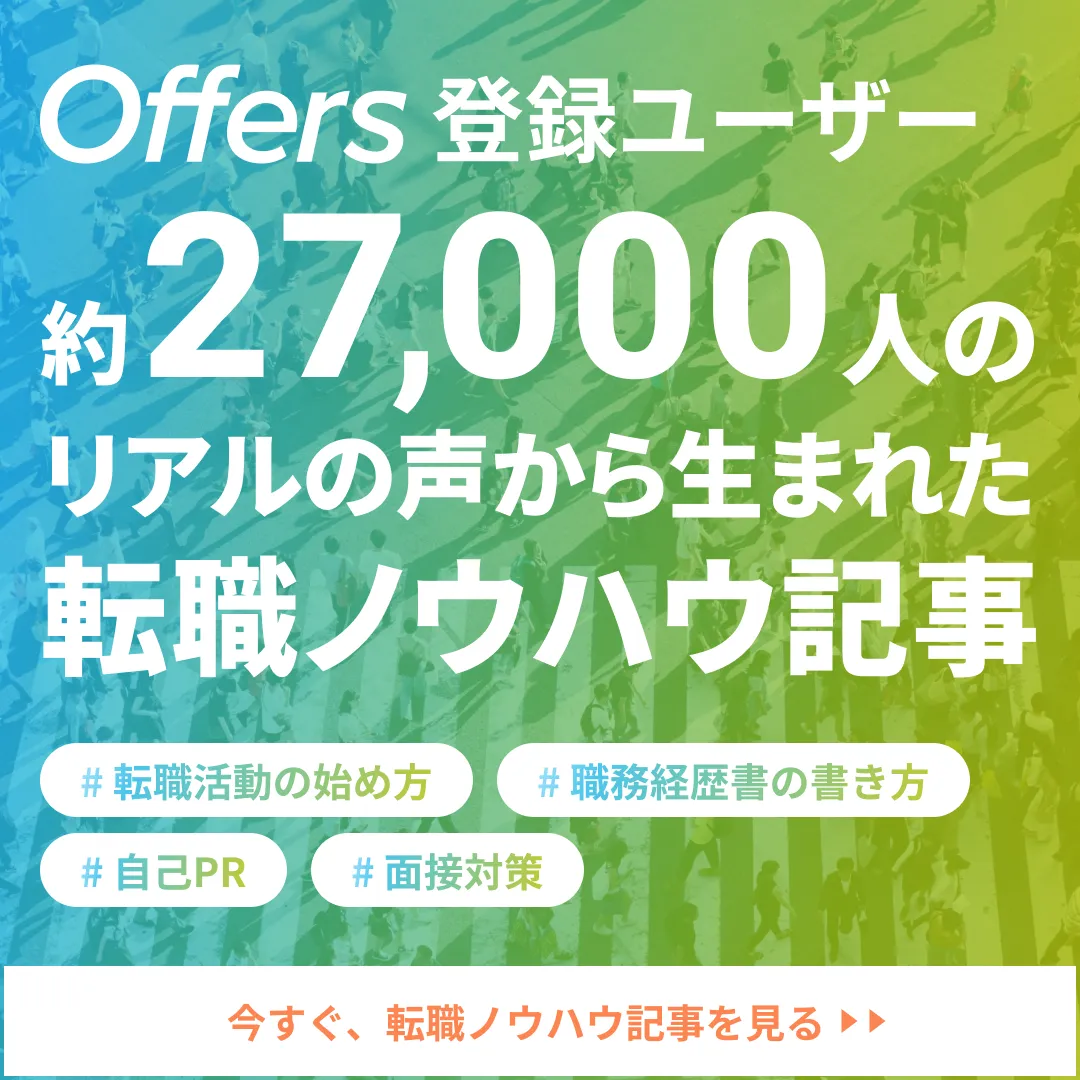
アカウントを作成して、求人情報のブックマークや応募の管理ができます。
求人に関するサマリ
SLIMは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発した小型月着陸実証機です。その名称は「Smart Lander for Investigating Moon」の略称で、日本語では「月面着陸技術実証機」と呼ばれています。SLIMの主な目的は、高精度な月面着陸技術の実証にあります。従来の月着陸機と比較して、SLIMははるかに小型で軽量な設計となっており、これにより打ち上げコストの削減と、将来的な月面探査ミッションの効率化を目指しています。
SLIMの役割は、単に月面に到達することだけではありません。その真の目標は、ピンポイント着陸と呼ばれる高度な技術の実証です。この技術により、目標地点から50〜100メートル以内という極めて狭い範囲に着陸することを目指しています。これは、月面上の特定の地質学的に興味深い地点や、将来的な月面基地の建設予定地など、正確な場所への着陸を可能にする重要な技術となります。
さらに、SLIMは月面の岩石組成を調査する役割も担っています。搭載されている分光カメラを使用して、月の岩石に含まれる鉱物の種類や分布を分析します。これにより、月の形成過程や進化に関する新たな知見を得ることが期待されています。SLIMのこれらの目的と役割は、日本の宇宙開発技術の高さを世界に示すとともに、将来的な月面探査や資源利用の可能性を広げる重要な一歩となるのです。
SLIMは、JAXAの月探査プログラムにおいて極めて重要な位置を占めています。日本の月探査の歴史を振り返ると、2007年に打ち上げられた月周回衛星「かぐや」が、月の詳細な地形図作成や重力場の測定など、科学的に価値の高いデータを収集しました。しかし、月面への着陸を実現したのはSLIMが初めてです。
JAXAにとって、SLIMは単なる技術実証機以上の意味を持っています。これは、日本の宇宙開発技術が新たなステージに進んだことを示す象徴的なプロジェクトなのです。特に、高精度な着陸技術の獲得は、将来的な月面基地建設や資源探査において、日本が主導的な役割を果たすための重要な一歩となります。
また、SLIMの成功は、国際的な月探査計画への日本の積極的な参加を後押しする要因となります。例えば、NASAが主導するアルテミス計画への日本の貢献度を高め、月面での持続的な活動における日本の存在感を強化することが期待されています。このように、SLIMはJAXAの月探査プログラムの中核を担う存在として、日本の宇宙開発の未来を切り開く重要な役割を果たしているのです。
SLIMの最大の特徴は、その高精度なピンポイント着陸技術です。この技術により、従来の月着陸機が数キロメートル単位の誤差で着陸していたのに対し、SLIMは目標地点から100メートル以内という驚異的な精度での着陸を目指しています。このピンポイント着陸を実現するために、SLIMは複数の革新的な技術を組み合わせています。
まず、SLIMは月面の画像認識技術を活用しています。搭載されたカメラが月面のクレーターや岩石の特徴を捉え、それを事前にプログラムされた地形データと照合することで、自機の位置を正確に把握します。この技術により、GPSが利用できない月面でも、精密な航法が可能となります。
さらに、SLIMは高度な姿勢制御システムを採用しています。複数のスラスターを巧みに制御することで、着陸直前まで機体の姿勢を細かく調整し、最適な軌道を維持します。これにより、強い月の重力や不規則な地形の影響を最小限に抑え、目標地点への精密な着陸を可能にしているのです。
SLIMには、その小型ボディに多数の高性能機器が搭載されています。これらの機器は、ピンポイント着陸の実現と月面の科学的調査の両方に貢献しています。主な搭載機器とその機能を以下に詳しく見ていきましょう。
まず、SLIMの「目」となる画像航法カメラが挙げられます。この高解像度カメラは、月面の詳細な画像を撮影し、機体の位置特定に不可欠な役割を果たします。また、分光カメラも搭載されており、これは月面の岩石に含まれる鉱物の種類や分布を分析するために使用されます。分光カメラのデータは、月の地質学的特徴を理解する上で重要な情報源となります。
さらに、SLIMには高精度の慣性航法装置が搭載されています。これは、機体の姿勢や速度を正確に測定し、ピンポイント着陸に必要な精密な制御を可能にします。また、レーザー高度計も搭載されており、月面からの正確な距離を測定することで、着陸の最終段階での制御をサポートします。
SLIMには、2台の小型月面探査ロボットが搭載されています。これらのロボットは、本体が着陸した後に展開され、月面の詳細な調査を行います。各ロボットの特徴と運用方法について、詳しく見ていきましょう。
1台目のロボットは「LEV-1」(Lunar Excursion Vehicle 1)と呼ばれ、直径約12センチメートルの球形をしています。LEV-1の主な役割は、月面の状況を観察し、画像データを地球に送信することです。球形の特徴を活かし、月面を転がりながら移動することができ、これにより効率的に広範囲の調査が可能となります。
2台目のロボットは「LEV-2」と呼ばれ、こちらはより小型で、LEV-1の内部に収納されています。LEV-2は、LEV-1から分離した後、独自に月面を探査します。特に、SLIMの着陸地点周辺の詳細な地形データを収集することが期待されています。これらのロボットの運用により、SLIMは着陸地点の周辺環境について、より多角的で詳細なデータを収集することができるのです。
SLIMの開発は、日本の月探査計画の一環として、長年の準備期間を経て実現しました。その開発の経緯とスケジュールを詳しく見ていきましょう。SLIMプロジェクトの構想は2008年頃から始まり、当初は「月着陸探査機」として計画されていました。しかし、予算や技術的な制約を考慮し、より実現可能な形へと計画が修正されていきました。
2013年、JAXAは正式にSLIMプロジェクトを承認し、本格的な開発がスタートしました。初期の段階では、主に基本設計と要素技術の開発に焦点が当てられました。特に、ピンポイント着陸技術の確立が最重要課題とされ、多くの研究者や技術者がこの挑戦的な目標に取り組みました。
2016年から2018年にかけては、SLIMの詳細設計が行われ、同時に各コンポーネントの製作も進められました。この期間中、地上での様々な試験が実施され、設計の妥当性や各機器の性能が綿密に検証されました。2019年には、SLIMの実機の組み立てが開始され、2020年後半には完成に至りました。
SLIMの打ち上げには、日本の主力ロケットであるH-IIAロケットが使用されました。H-IIAロケットは、これまで多くの人工衛星や探査機を宇宙に送り出してきた信頼性の高いロケットです。SLIMの打ち上げは、2023年9月7日に鹿児島県の種子島宇宙センターから行われました。
打ち上げに使用されたH-IIAロケットは、2段式の液体燃料ロケットで、全長約53メートル、直径約4メートルの大型ロケットです。1段目にはLE-7Aエンジン、2段目にはLE-5Bエンジンが搭載されており、これらの強力なエンジンがSLIMを地球の重力圏から脱出させ、月への軌道に乗せる役割を果たしました。
打ち上げ当日は、天候にも恵まれ、予定通りのスケジュールで打ち上げが実施されました。ロケットは打ち上げ後約16分で予定の軌道に到達し、その後SLIMは無事にロケットから分離されました。この打ち上げの成功は、日本の宇宙開発技術の高さを改めて世界に示す機会となりました。
SLIMの月への旅は、打ち上げ成功後も長く険しいものでした。地球を出発してから月面着陸までの約4か月間、SLIMは様々な挑戦に直面しました。まず、打ち上げ直後の初期運用フェーズでは、すべてのシステムの健全性確認が行われました。太陽電池パネルの展開や通信系の確立など、重要な初期動作がすべて正常に完了したことが確認されました。
その後、SLIMは地球周回軌道から月遷移軌道へと移行しました。この過程では、精密な軌道制御が必要とされ、搭載された推進系が何度も微調整を行いました。月への接近が始まると、SLIMは月の重力の影響を受けて軌道を変化させていきます。この段階では、地上管制チームとの緊密な連携のもと、常に最適な軌道を維持するための調整が続けられました。
SLIMの月面着陸地点は、慎重に選定されました。最終的に選ばれたのは、月の表側にある「シラコワ」クレーター近傍の平坦な地域です。この地点は、科学的な価値が高いとされる「月の海」と呼ばれる玄武岩平原の端に位置しています。着陸地点の選定には、地形の平坦さ、科学的興味、そして通信の容易さなど、複数の要因が考慮されました。
月への接近段階では、SLIMは月を周回する軌道に投入されました。この周回軌道から、徐々に高度を下げていき、最終的な着陸フェーズに備えます。着陸の直前には、SLIMは月面の詳細な画像を撮影し、それを基に最終的な着陸地点の微調整を行いました。この過程で、SLIMの革新的なピンポイント着陸技術が遺憾なく発揮されたのです。
2024年1月20日、SLIMは予定通り月面着陸を試みました。着陸の最終段階では、搭載されたカメラやセンサーが月面の状況をリアルタイムで分析し、最適な着陸姿勢を維持しながら、ゆっくりと高度を下げていきました。この緊張の瞬間、地上の管制チームと世界中の科学者たちが固唾を呑んで見守る中、SLIMは月面への軟着陸を成功させたのです。
SLIMの月面着陸成功後、JAXAは直ちに着陸後の状況確認を開始しました。初期の通信で、SLIMの主要システムが正常に機能していることが確認されました。しかし、着陸直後に予期せぬ問題が発生しました。SLIMの太陽電池パネルが月面に向いてしまい、十分な発電ができない状態に陥ったのです。この状況下で、JAXAの管制チームは迅速な対応を迫られました。
限られた電力の中、SLIMは予定されていた初期観測を実施しました。搭載されたカメラによって、着陸地点周辺の詳細な画像データが地球に送信されました。これらのデータは、ピンポイント着陸の精度を検証する上で非常に重要なものでした。また、分光カメラによる月面の鉱物組成の分析も、短時間ながら実施されました。
電力不足の問題に対し、JAXAは創意工夫を重ねました。月の公転に伴う太陽光の角度変化を利用し、太陽電池パネルへの光の当たり方を改善させる試みが行われました。この努力の結果、一時的に電力供給が回復し、追加のデータ送信が可能となりました。しかし、安定した電力供給の確保には至らず、SLIMの運用は断続的なものとなりました。
SLIMのミッションは、いくつかの重要な成果を達成しました。最も注目すべき成果は、高精度なピンポイント着陸の実証です。JAXAの発表によると、SLIMは目標地点から約55メートルの範囲内に着陸することに成功しました。これは、当初の目標である100メートル以内を大きく上回る精度であり、世界的に見ても極めて高い技術力を示すものです。
また、SLIMは月面の詳細な画像データを取得することにも成功しました。これらの画像は、着陸地点周辺の地形や岩石の分布を明らかにし、月の地質学的研究に貴重な情報をもたらしました。特に、分光カメラによって得られた鉱物組成のデータは、月の形成過程や進化に関する新たな知見を提供する可能性を秘めています。
一方で、SLIMは予期せぬ挑戦にも直面しました。太陽電池パネルの問題は、宇宙探査におけるリスクと不確実性を改めて浮き彫りにしました。しかし、この問題に対するJAXAの迅速な対応と創意工夫は、困難な状況下での宇宙機器の運用に関する貴重な経験となりました。この経験は、今後の月探査ミッションの設計や運用計画に活かされることでしょう。
SLIMの成功は、日本の月探査計画に大きな影響を与えることが予想されます。まず、ピンポイント着陸技術の実証は、将来の月面探査ミッションの可能性を大きく広げました。この技術により、科学的に重要な地点や、将来の月面基地建設に適した場所への正確な着陸が可能となります。JAXAは、この技術を基盤として、より野心的な月探査計画を立案することができるでしょう。
さらに、SLIMの成功は国際協力の機会も拡大させました。例えば、NASAが主導するアルテミス計画への日本の貢献度が高まることが期待されます。SLIMで実証された技術は、国際的な月面探査プロジェクトにおいて、日本の重要性を高める要因となるでしょう。これにより、日本は月の持続的な探査や利用に関する国際的な議論において、より強い発言力を持つことができるようになるかもしれません。
また、SLIMの経験は、将来の探査機の設計にも影響を与えるでしょう。特に、予期せぬ問題に対する対応策や、限られたリソースでの効率的な運用方法など、実践的な知見が今後の探査機開発に活かされることが期待されます。これらの経験は、月だけでなく、火星や小惑星など、他の天体への探査計画にも応用される可能性があります。
SLIMの月面着陸成功は、日本国内で大きな反響を呼びました。政府や学術界、そして一般市民からも、この快挙に対して多くの称賛の声が寄せられました。特に、日本の宇宙開発技術の高さを示す象徴的な出来事として、広く認識されています。
政府関係者からは、SLIMの成功が日本の宇宙開発戦略に与える影響の大きさが強調されました。文部科学大臣は、「この成果は日本の宇宙技術の卓越性を世界に示すものであり、今後の宇宙開発における日本の国際的地位向上につながる」とコメントしています。また、経済界からも、この技術が将来的に産業応用される可能性に期待が寄せられています。
学術界では、SLIMのミッションが月の地質学的研究に与える影響に注目が集まっています。日本地球惑星科学連合の関係者は、「SLIMが取得したデータは、月の形成過程や進化に関する新たな知見をもたらす可能性がある」と評価しています。また、若手研究者や学生の間でも、宇宙開発への関心が高まっており、将来の人材育成にも好影響を与えると期待されています。
SLIMの成功は、国際的にも高い評価を受けています。特に、ピンポイント着陸技術の実証は、世界の宇宙機関から注目されました。NASAのアルテミス計画の責任者は、「SLIMの技術は、将来の月面探査において極めて重要な役割を果たすだろう」とコメントしています。欧州宇宙機関(ESA)からも、日本の技術力への賞賛の声が上がっています。
また、SLIMの小型・軽量設計は、宇宙開発のコスト効率化の観点からも評価されています。インドやイスラエルなど、新興の宇宙開発国からは、SLIMのアプローチを参考にしたいという声も聞かれます。これは、宇宙開発の民主化につながる可能性があるとして、国際的に注目されています。
一方で、SLIMが直面した電力問題に対する日本の対応も、国際的に評価されています。予期せぬ問題に対する迅速な対応と創意工夫は、宇宙探査における重要な教訓として認識されています。この経験は、今後の国際的な宇宙ミッションの計画立案や危機管理にも影響を与えるでしょう。
総じて、SLIMの成功は日本の宇宙開発技術の高さを世界に示すとともに、国際的な月探査計画における日本の重要性を高めました。今後、日本がこの成果をどのように活かし、さらなる宇宙開発の発展につなげていくかが、世界から注目されています。SLIMの成功は、単なる一つの探査機のミッション成功にとどまらず、人類の月探査の新たな章を開く重要な一歩となったのです。
エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職採用サービス「Offers(オファーズ)」では、非公開求人を含む豊富なIT・Web業界の転職・副業情報を提供しています。高年収の求人・高時給の案件や最新技術スタックを扱う企業など、あなたのスキルを最大限に活かせるポジションが見つかります。専任のキャリアアドバイザーが、入社日調整や条件交渉をきめ細かくサポート。転職・正社員求人、副業・業務委託案件、募集をお探しの方はOffersまでご相談ください。閉じる
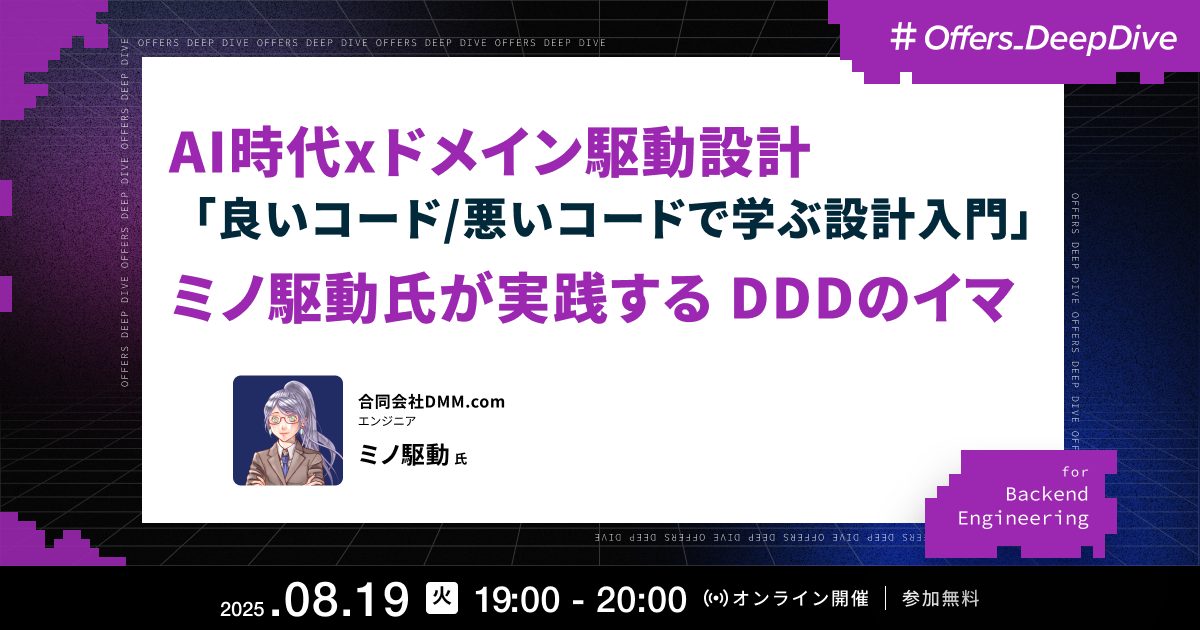
開催前
昨今、AIコーディングエージェントの進化と普及により、ソフトウェア開発はかつてないほど、加速しています。 さらにはコーディングだけでなく設計もAIに任せる場面も増え、「AI時代になれば、DDD(ドメイン駆動設計)のような手法はもう必要なくなるのでは?」そんな疑問を抱くエンジニアも多いのではないでしょうか。 今回のイベントでは、「良いコード/悪いコードで学ぶ設計入門」のミノ駆動氏をお招きし、AI時代におけるDDDの在り方と新しい実践アプローチについて直接お話しいただきます。 AIによってDDDは不要になるのか、それとも在り方が変わるのか。ソフトウェア設計の第一線で活躍するミノ駆動氏が実践するDDDの在り方を伺うことで、今後の設計の在り方について理解する場になりましたら幸いです。
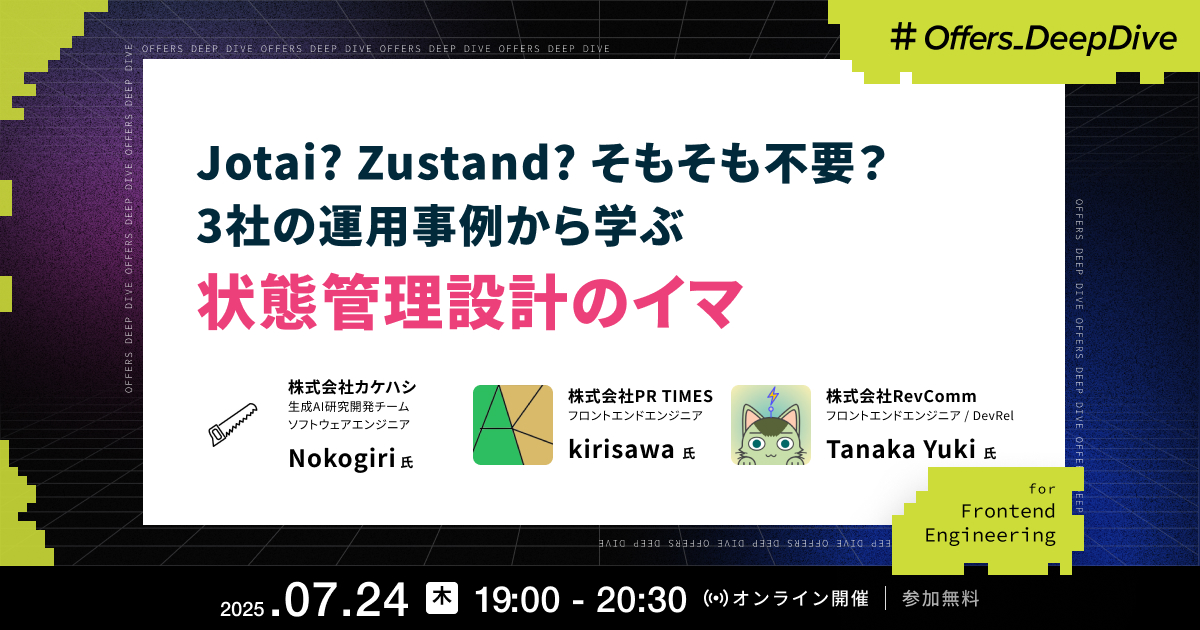
アーカイブ公開中
React開発において「状態管理」は避けて通れないテーマです。一方で「結局React標準のContext APIだけで十分?」「Recoilのメンテナンスが停止したけど次は?」「JotaiとZustandはどう違う?」といった疑問を抱えたまま、なんとなく導入を進めているケースも多いのではないでしょうか。 今回は、状態管理に関してJotai・Zustand・React標準のContext APIという異なるアプローチを取る3社をお招きし、実際の技術選定の背景や本番運用、移行の過程で得た知見を深掘りしていきます。 それぞれが採用・運用してきたライブラリのメリット・デメリットを共有しながら、各社の技術選定基準や設計方針、移行時の苦労と工夫まで、リアルな運用知見を語り合います。 「状態管理ライブラリ、今結局何を選ぶべき?」とモヤモヤを抱えている方や正解が見出せていない領域だと感じる方におすすめです。ぜひご参加ください。
開催日:
2025年7月24日(木)19:00~20:30
.jpg)
アーカイブ公開中
プロダクト開発の現場で「アクセシビリティ」という言葉を耳にする機会は、ここ数年で確実に増えています。一方でその多くは、「法律で求められているから」「顧客に言われたから」「上からの指示だから」といった受け身の対応にとどまっていることも少なくありません。 また、「高齢者や障害者向けの話で、自分たちには関係ない」「何をすればいいのか正直ピンとこない」と感じている方も多いのではないでしょうか。 そこで本イベントでは、デザイナーやエンジニアとしてアクセシビリティの分野で活躍するフリー株式会社 アクセシビリティスペシャリストの伊原力也氏、UIデザイナー兼フロントエンドエンジニアのymrl氏、株式会社 Helpfeel でエンジニアを務めるPasta-K氏という豪華メンバーをお招きし、そもそもなぜアクセシビリティが必要なのか、アクセシビリティは通常のプロダクト開発と比較した時に、どの程度の優先度なのか。本当にコストに見合うのか?といったリアルな疑問について伺います。 「アクセシビリティ」は自分にはまだ関係ないと思っている方、開発現場におけるリアルな取り組みを知りたい方、アクセシビリティの実装や設計に興味のある方、良いプロダクト開発を実現したいと考えている方にとって、有意義な対話の場となることを目指します。ぜひご参加ください! 🧑💻イベントでわかること アクセシビリティを実際にどの優先度で考えるべきなのかがわかる 建前でのアクセシビリティへの向き合い方ではなく、本音でどう向き合うべきかがわかる 自身の会社で本当にアクセシビリティを取り組む必要があるのか?という疑問がわかる
開催日:
2025年7月9日(水)19:00~20:30
.png)
アーカイブ公開中
昨今、AIコーディングエージェント(例:CursorやClineなど)の進化と普及により、ソフトウェア開発はかつてないほど、加速しています。 しかし同時に、PMから渡された仕様をエンジニアがそのままAIエージェントに読み込ませ、生成されたコードを使っただけでは、リリースに耐える品質を担保するのは難しいのが現実ではないでしょうか。 今回のイベントでは、AI駆動開発と実際に向き合ってきたPMのmiyattiさん、エンジニアのkagayaさんをお招きし、現場で直面しているAI駆動開発の限界や求められる品質基準について、それぞれの立場からお話しいただきます。 PMとエンジニア、両者の視点からAI駆動開発の“今”と“これから”を改めて考え直す貴重な機会です。AIを開発に取り入れている方、これから取り入れたいと考えている方、そして、PMとエンジニアの連携に課題意識を持っている方に、ぜひご参加いただきたい内容です。
開催日:
2025年6月24日(火)19:00~20:00
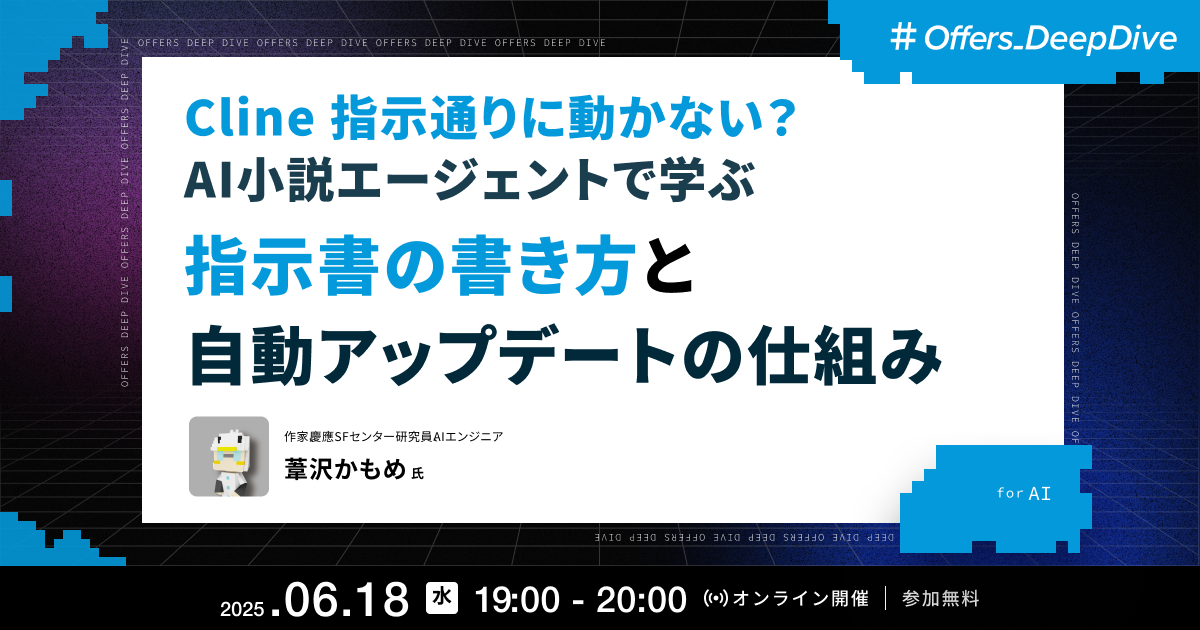
アーカイブ公開中
ClineやCursorなどの生成AIツールが急速に広がる中、「うまく動かない」「どこまで読み込ませるべきか分からない」そう感じることはありませんか? 本イベントでは、小説執筆という膨大な情報を扱う創作プロセスを題材に、下記のような、生成AIを意図通りに動かすための設計ノウハウを学べます。 - どういった情報をAIに読み込ませるべきかの切り分け - セッションをまたぐ長大なコンテキストを保持するための設計(Memory Bankの活用) - コードや文章を生成後に行うプロンプトの更新方法、およびその自動化 >※メモリバンクのURL: [https://docs.cline.bot/prompting/cline-memory-bank](https://docs.cline.bot/prompting/cline-memory-bank) Clineを中心に据えながらも、CursorやObsidianとの比較や、「そもそもAIに任せるべき部分・任せるべきでない部分はどこか?」という、今後の実務においても避けては通れない問いを扱う予定です。 Clineを導入しているものの、活用に課題を感じている方や、プロンプト設計に体系的な知見を持ちたい方にとって、有意義な学びの機会となる内容です。ぜひ、ご参加ください。
開催日:
2025年6月18日(水)19:00~20:00