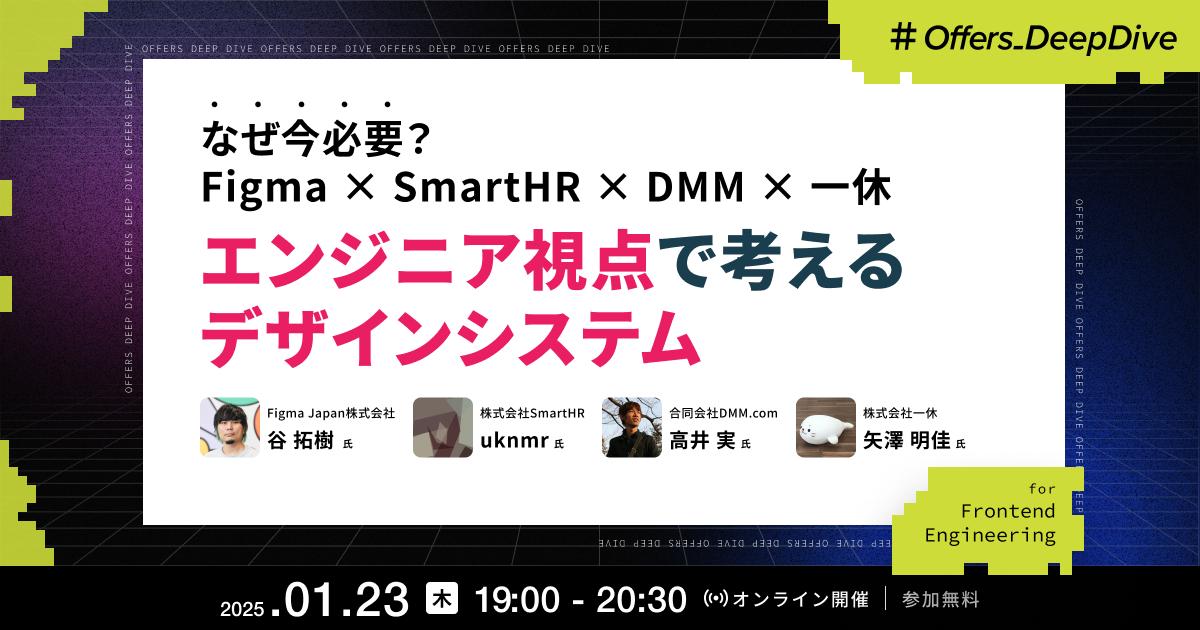エンジニアが転職を考える理由ランキングTOP10
エンジニアが実際に転職を決意する理由にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは最新の調査結果や業界知見をもとに、代表的な転職理由トップ10をランキング形式で紹介します。
1位:新しい技術を身に付けたい・スキルアップを図りたい
技術革新の速いIT業界において、新しい技術への挑戦欲求はエンジニアの転職理由のトップに挙げられます。今の職場では触れられない最新の開発言語やフレームワークを習得し、自身の市場価値を高めたいと考えるエンジニアは少なくありません。
実際、スキルアップや自己成長を求める声は強く、先述の調査でも「スキルアップしたい」が転職理由として上位にランクインしています。
常に新技術をキャッチアップし続けることはエンジニアにとってキャリア上必要不可欠であり、「このままでは時代に取り残されるのではないか」という不安から転職に踏み切るケースもあります。
最新技術を扱うプロジェクトに参加できる企業や、学習支援制度が充実した環境を求めて転職を検討するのは、前向きなキャリア志向の表れと言えるでしょう。
2位:給与・待遇への不満
収入面の不満は多くのエンジニアに共通する転職理由です。先述のとおり、IT業界の転職理由ランキングでも「給与を上げたい」がほぼ不動の1位となっています。高度なスキルや経験に見合った報酬を得られていないと感じたり、昇給のペースが遅かったりすると、エンジニアは「他社ならもっと評価されるのでは?」と考え始めます。
特に、近年はエンジニア不足により他社が高待遇で人材を募集するケースも多いため、自身の市場価値と現在の待遇との差を意識しやすくなっています。
「現在の年収は適正だろうか?」と疑問を持ち、客観的に市場相場と比較した上で転職活動に踏み切るエンジニアも増えているのです。
3位:会社や業界の将来性に不安がある
自社の将来性や安定性への不信感から転職を考えるパターンです。技術トレンドの変化が激しい業界だけに、自社プロダクトが時代遅れになっていたり、ビジネスモデルが停滞していたりすると、エンジニアはキャリアの先行きに不安を覚えます。
「この会社にいて成長できるのか?事業は持続するのか?」という疑問が募ると、より成長性の高い企業や将来有望な分野へ移りたいと考えるようになります。
例えば、業界全体が縮小傾向にある場合や、自社の財務状況が悪化して新規開発投資が減っている場合など、外的要因による不安も理由の一つです。
こうした場合、エンジニアは自身のキャリアを守るため、将来性のあるプロダクトや安定した経営基盤を持つ企業への転職を視野に入れる傾向が強まります。
4位:ワークライフバランスの悪化(長時間労働・休日出勤など)
働き方や労働環境への不満も近年大きな転職理由となっています。長時間労働や度重なる休日出勤、深夜対応などで心身に負担を感じ、「このままでは自分の生活が成り立たない」と転職を決断するケースです。特にコロナ禍以降リモートワークが普及したことで、柔軟な働き方を求める意識がエンジニアの間でも高まりました。
そのため、未だにハードな働き方が常態化している企業から、フレックスタイム制や在宅勤務制度が整った企業へ移る動きが増えています。
労働時間に関する不満は全年代・全職種でも上位に入る普遍的な問題であり、前述のように2024年は法改正も相まって注目度が上がっています。
エンジニアにとっても、クリエイティブな仕事を長く続けるには心身の健康が不可欠であるとの認識が広がっており、ワークライフバランスの良い職場を求める傾向は今後も続くでしょう。
5位:昇進・キャリアアップが望めない
現職で役職や役割の限界を感じ、さらなるキャリアアップを求めて転職を考えるケースです。
「いつまで経ってもポジションが上がらない」「重要なプロジェクトを任せてもらえない」といった状況では、意欲的なエンジニアほど欲求不満に陥ります。
特に設計や要件定義など上流工程に関わりたい、マネジメントにも挑戦したいといった希望を持つ人は、現職でチャンスが無ければ他社でその機会を探そうとします。
実際、一般的な転職理由ランキングでも「昇進・キャリアアップが望めない」が上位に挙がっており、将来のキャリアビジョンを描けないことは大きな不安要因です。
エンジニアの場合、技術スペシャリストの道を極めたい人もいればマネージャー志向の人もいますが、いずれにせよ自身の成長の停滞を感じたら転職によって打開しようとする傾向があります。
6位:現職での評価に不満(正当に評価されない)
努力や成果が適切に評価されないと感じることも、転職を決意させる大きな要因です。例えば、明確な評価基準がなかったり上司の主観で評価が左右されたりする職場では、エンジニアのモチベーションが下がりがちです。
「自分はこれだけ貢献しているのに昇給や昇進に繋がらない」「他の同僚と比べて不公平だ」といった不満が蓄積すると、公平な評価制度のある会社への転職を考えるようになります。
エンジニアは成果が数値で見えづらい部分もある職種ですが、だからこそ評価制度の透明性を重視する人が多くなっています。
適材適所でスキルを伸ばせる環境や、成果主義で報酬に反映してくれる企業を求める動きが背景にあります。
7位:職場の人間関係・社風の問題(働く環境の悪さ)
人間関係の悪化や職場環境のミスマッチも、転職理由として頻出です。チーム開発の多いエンジニア職において、人間関係のストレスは生産性に直結します。「上司との折り合いが悪い」「社内の雰囲気がギスギスしている」など、職場に居づらさを感じて転職するケースは後を絶ちません。
一般的な調査でも「人間関係が悪い/合わない」が常に上位にランクインしており、IT業界も例外ではありません。
また、人間関係だけでなく企業文化や風土も重要です。例えば、挑戦を好むエンジニアが保守的な文化の会社にいると窮屈に感じたり、逆に落ち着いた環境を望む人がベンチャー気質の社風に疲弊したりすることがあります。
自分の価値観に合う社風やメンバーと働きたいという思いから、「もっと風通しの良い環境で働きたい」「社員同士が尊重し合う文化の会社に行きたい」といった理由で転職を検討するわけです。
8位:キャリアチェンジ(他にやりたい分野・職種が見つかった)
エンジニアとしてキャリアを積む中で、別の分野に挑戦したくなることもあります。たとえば、Webエンジニアから機械学習エンジニアへ、開発者からプロジェクトマネージャーへ、あるいはエンジニア職自体から企画職や起業家へといったキャリアチェンジの道です。
現在の仕事が嫌いなわけではなくとも、新たな情熱を注げる分野を発見した場合、それを追求するために転職という選択肢を取る人も少なくありません。
「他にやりたい仕事が見つかった」という理由はランキングでも上位に挙がる傾向があり、20代〜30代の比較的若手エンジニアを中心に見られます。
急成長中の技術領域(例:AI、ブロックチェーンなど)や別職種への興味が高まり、「今が転職の好機」と判断して異業種・異職種に飛び込むケースもあるでしょう。
これはポジティブな転職理由であり、本人のキャリアビジョンが明確なほど成功しやすいタイプの転職と言えます。
9位:自身の市場価値を高めたい(経歴・スキルのブラッシュアップ)
市場価値向上を目的とした戦略的な転職も、エンジニアには見られます。より知名度の高い企業で経歴を積むことで履歴書の価値を上げたい、先進的なプロダクトに関わって希少なスキルを身につけたい、といった動機です。将来的にフリーランスや起業を考えているエンジニアが「武器になる実績を得たい」という思いから転職するケースもあります。
長期的視点に立った前向きな理由ではありますが、常に転職が最善とは限らないため、タイミングと目的の明確化が重要です。
10位:会社都合の異動・転勤への不満
最後に、会社側の事情による配置転換が転職のきっかけとなるケースです。日本の企業では異動・転勤が付き物ですが、エンジニアにとって望まない部署異動や遠方への転勤は時に大きな負担となります。
家族の事情やライフスタイルとの両立が難しくなったり、専門外の部署への異動でキャリアが停滞する恐れが出たりするためです。
「転勤を命じられたが家庭の事情で難しい」「希望しない職種への異動が決まってしまった」といった場合、エンジニアは自分のキャリア主導権を取り戻すために転職を選ぶことがあります。
特に近年は働き方の多様化により、地域限定で働きたい・特定分野の仕事を続けたいという希望が尊重される傾向にあります。
そのため、無理な異動辞令に従うよりも、最初から希望勤務地・職種が明確な企業へ転職し直すという判断に至るわけです。
離職防止に向けて中小企業が取るべき打ち手
若手エンジニアの離職を防ぐために、中小企業の経営者・マネジメント層ができる具体的な施策を整理します。ポイントは、前述した転職理由を裏返し、エンジニアが「辞めたい」と感じにくい職場づくりをすることです。
公正な評価と適切な報酬改善
「成果を出しても評価されない」「給与が上がらない」という不満を放置しないことが重要です。中小企業は大企業ほど高給を出せなくても、努力やスキルに見合った昇給・賞与で応える姿勢を示しましょう。
例えば評価制度を見直し、年功序列ではなくスキルや貢献度を反映する仕組みにすることです。
実力ある若手が正当に評価されれば、「この会社でも成長しながら報われる」という安心感が生まれ、給与不満による転職衝動を和らげられます。
年功序列への不満を解消するためにも、定期的な昇給機会や成果に応じた報奨制度の導入が有効です。
キャリアアップ機会の提供と成長支援
「このままでは成長できない」と感じさせない工夫が必要です。エンジニアが最新技術に触れたり新たな役割に挑戦できる機会を意図的に作りましょう。具体的には、社内勉強会やカンファレンス参加支援、資格取得補助などのスキルアップ支援制度を整える、意欲ある社員には難易度の高いプロジェクトを任せてみる、あるいは希望に応じて部署異動やローテーションで様々な開発経験を積めるようにする等が考えられます。
小規模企業でも明確なキャリアパスを提示し、「数年後にはリーダーになれる」「フルスタックエンジニアを目指せる」といった未来像を示せば、腰を据えて社内で成長しようという意欲につながります。
エンジニア自身が市場価値を高められる環境を用意することが、成長志向の人材の流出防止に直結します。
働きやすい職場環境と人間関係の改善
ハラスメントの根絶とオープンなコミュニケーション文化づくりは離職防止の基本です。経営者自らが風通しを良くし、現場の声に耳を傾ける姿勢を示しましょう。パワハラ・セクハラが起きにくいよう管理職研修を行ったり、万一の相談窓口を設置したりして、安心して働ける職場にします。
また、メンター制度や1on1ミーティングなどで若手エンジニアの悩みを早期にキャッチしケアすることも有効です。
先輩社員との座談会を設けて技術やキャリア相談ができるようにするなど、社内の人間関係を良好に保つ施策を積極的に取り入れてください。
尊敬できる上司・先輩がいて成長をサポートしてくれる環境であれば、「人間関係の悪さ」を理由に辞めたいとは思わないはずです。
柔軟な働き方の導入(リモート・残業削減など)
ワークライフバランスの改善はエンジニア定着のカギです。中小企業でも可能な範囲でテレワークやフレックスタイム制を導入し、社員の事情に合わせて柔軟に働けるよう検討しましょう。特にIT人材はPCさえあれば業務遂行できるケースが多いため、週数日の在宅勤務やフルリモート可とすることで全国から優秀な人材を採用・維持できる可能性も高まります。
また、長時間労働が常態化していないか見直し、残業を減らす業務改善や人員配置の最適化にも取り組みましょう。育児中や介護中の社員への配慮(時短勤務など)を行うことも大切です。
「家庭の事情に配慮がない」という不満を出させないためにも、社員それぞれのライフステージに合わせた柔軟性を確保することが離職防止につながります。
ビジョン共有とエンゲージメント向上
会社の将来像や事業ビジョンを社員と共有し、共感を育むことも有効な施策です。経営層がしっかりと企業の方向性を示し、「このプロダクトで業界トップシェアを目指す」「◯年後に上場を目標に成長中だ」など明るい展望や目標を伝えることで、社員の将来不安を和らげます。
若手にも戦略をオープンに語り、「一緒に会社の未来を創っていこう」という参加意識を持ってもらいましょう。
加えて、定期的な1on1面談やアンケートで社員の満足度や不安点を把握し、フィードバックを基に職場環境を改善する姿勢も示してください。
多くの場合不満は表面化せず蓄積し、手遅れになってから離職という形で噴出します。
これを防ぐには、経営陣・上司から積極的に働きかけて「最近どう?」と声をかける文化を作ることです。早めに悩みを聞き出し対処できれば、退職の決断を思い留まらせるチャンスにもなります。
近年の転職理由にみる変化
では、こうした転職理由に近年変化はあるのでしょうか?基本的な傾向は大きくは変わらないものの、働き方に関する意識や価値観の幅が広がっている点が注目されます。
リモートワーク志向の高まり
コロナ禍を経て、リモートワークの可否はエンジニアにとって重要な要素となりました。「リモート勤務を続けたい」「勤務地に縛られず働きたい」と考えるエンジニアが増え、逆にリモートを廃止して出社に戻す企業では離職者が相次ぐケースも報告されています。
近年は在宅勤務やハイブリッド勤務を当たり前と考える風潮が若手を中心に根付いており、リモート環境が整っていない職場は敬遠されがちです。価値観・重視ポイントの多様化
一昔前であれば「安定した大企業で定年まで勤める」ことが善とされていましたが、現在の若手はそれぞれ自分なりのキャリア観・働き方観を持っています。
そのため、「この会社で成長できない」「自分のやりたいことと合わない」と感じれば、早期に見切りをつけることも珍しくありません。近年では特に「働きやすさ」と「自己成長」の双方を追求する傾向が指摘されています。
また、経済環境の変化もあり「会社の安定性」を気にする声が増え*点も見逃せません。コロナ禍や景気変動を経験し、事業の先行きに不安を覚え転職に踏み切る人が増えています。
一方で「どうせ転職するなら成長中の企業や新しい働き方に対応している企業が良い」という考えから、柔軟な働き方を整備し成長を続けている企業に人気が集まる傾向もあります。
つまり、安定志向と成長志向の二極化とも言える価値観の多様化が進んでいるのです。
採用ブランディングに活かせる視点と工夫
優秀なエンジニアに「選ばれる会社」になるための採用ブランディングのポイントを解説します。
離職を防ぐだけでなく、将来の採用活動にも今回の知見を活かし、求人応募者に自社の魅力を的確に伝えることが大切です。
以下の視点を押さえておくと、中小企業でもエンジニア採用市場で存在感を高められるでしょう。
求人票でエンジニア目線の情報を充実させる: 採用の入り口である求人票(求人広告)には、エンジニアが知りたい情報をできるだけ盛り込むようにします。具体的には、仕事内容の詳細(扱う技術スタックやプロジェクト内容*はもちろん、開発手法、開発環境、使用ツール、チーム体制、評価制度、上司やメンバーのプロフィールなどです。
これらはエンジニアが転職先を判断する重要な軸であり、十分に開示することでミスマッチを減らせます。
また、「リモート可」「フレックス制度あり」「平均残業時間◯時間」といった働き方の情報や、「明確な評価基準に基づき年2回昇給チャンスあり」など待遇・制度面の安心材料も訴求ポイントです。
求人票は単なる募集要項ではなく、自社のアピールの場と捉え、エンジニアに刺さるキーワードを盛り込んでください。
柔軟な働き方や成長環境をアピールする
前述のとおり、若手エンジニアは働き方の柔軟性と成長機会を重視します。「リモートワークOK」「副業可」「裁量労働制で自分のペースで働ける」などの柔軟な環境があるなら、それを前面に打ち出しましょう。
柔軟な働き方を提供できること自体が大きな魅力になり得ます。 また、スキルアップ支援(研修制度・書籍購入補助・資格取得奨励など)やキャリアパスの情報も盛り込むと、「この会社なら成長できそうだ」と感じてもらえます。特にZ世代の若手には「働きやすさ」と「自己成長」の両面を訴求することが効果的とされています
採用面接で求職者のモチベーションに寄り添う
採用面接の場では、単にスキルや経歴を確認するだけでなく、相手の転職理由やキャリア志向を深くヒアリングすることが重要です。
面接官はこちらから質問するだけでなく、自社の方針やカルチャーも積極的に共有し、求職者の不安を解消する対話を心がけます。
例えば「前職ではどういった点で物足りなさを感じましたか?」と尋ね、その回答(「新しい技術に挑戦できなかった」等)に対して自社ではどんな機会があるかを具体的に伝える、といった対応です。
これは双方のミスマッチ防止にも役立ちますし、求職者に「自分の希望を理解してくれそうな会社だ」という安心感を与えます。
また、面接官(特にエンジニア出身の担当者)は謙虚かつ熱意を持って自社の魅力を語りましょう。応募者は転職理由から自分の将来を真剣に考えているものなので、こちらも本気で応えようとする姿勢が伝われば、志望度の向上につながります。
面接は評価の場であると同時に自社を売り込む場でもあることを意識してください。
社内カルチャーや社員の声を発信する
エンジニアが働く雰囲気や価値観を伝えるために、積極的に社内の様子を情報発信しましょう。具体的には、自社エンジニアのインタビュー記事やブログ、SNS投稿などでリアルな声を発信する方法があります。
例えば「なぜ当社に入社を決めたのか」「現在どんなやりがいを感じているか」といった社員の本音を、自社サイトの採用ページやNote記事、Twitterなどで紹介します。最近では社員が自社について語るSNS発信や社員紹介経由の採用が注目されており、エンジニアの「リアルな声」が求職者の心に響くケースも増えています。
中小企業の場合、大企業に比べ知名度が低い分、自社のカルチャーを具体的にイメージさせる工夫がより重要です。
オフィスの写真や勉強会の様子、チームで写った楽しそうな集合写真なども効果的でしょう。こうした発信により、「社員同士仲が良さそう」「技術に熱心な社風だな」と感じてもらえれば、企業ブランドの向上に直結します。
エンジニア志向に寄り添った採用メッセージ
最後に、ブランディング全般に言えることですが、ターゲットであるエンジニアの志向に寄り添う言葉遣いとメッセージを心がけます。
例えば、「最新技術に触れられる」「コード品質を重視する文化」「ユーザーの声を直接聞きながら開発できる」といったフレーズは、多くのエンジニアにとって魅力的に映るでしょう。
一方で、あまりに抽象的な理念や宣伝的な文句ばかりでは響きません。具体的なエピソードや実績を交えて、「少人数チームでも月間◯万ユーザーのサービスを支えるスケーラブルな開発を実現」などリアリティのある表現で自社の良さを伝えましょう。
また、募集要項や面接で嘘をつかないことも大前提です。入社後に話が違うとなれば早期離職に直結するため、誠実で透明性のある情報開示こそが信頼されるブランド作りにつながります。
おわりに
日本の若手~中堅エンジニアが転職を考える主な理由とその背景、そして離職防止・採用ブランディングのポイントについて解説しました。
まとめると、エンジニアが会社を去るときには必ず理由があり、それは給与・成長・人間関係・働き方・将来性といった要素に集約されます。
経営者にとって重要なのは、自社の現状を客観視し、エンジニアの視点に立って改善を続けることです。
離職率の高まりに悩む場合は、まず何が彼らの不満になり得るか洗い出し、一つ一つ手を打っていきましょう。「
人が資産」である中小企業だからこそ、人を大切にする経営が最終的に企業価値を高める」という視点を持つことが肝心です。
また、これから採用戦線に挑む際も、単に求人を出すだけでなく、エンジニアに選ばれるためのブランディングを意識してみてください。
柔軟な働き方、成長できる環境、良いチーム文化――これらを備えているなら遠慮なく発信し、もし不足があるなら少しでも整えていく努力を見せることです。幸いIT業界では、良い取り組みはSNS等で社員から自然と発信され評判となることもあります。社内の改善と情報発信を積み重ねていけば、離職防止と採用力強化は相乗効果で実現できます。
若手・中堅エンジニアの流動性が高まる時代だからこそ、企業も変化を恐れず働きやすい魅力的な職場づくりに挑戦しましょう。
その積み重ねが「この会社で働き続けたい」「ここで働いてみたい」と思われる強いブランドを生み出すのです。社員が定着し成長し続けることで、結果的に企業の持続的な発展にもつながっていくでしょう。