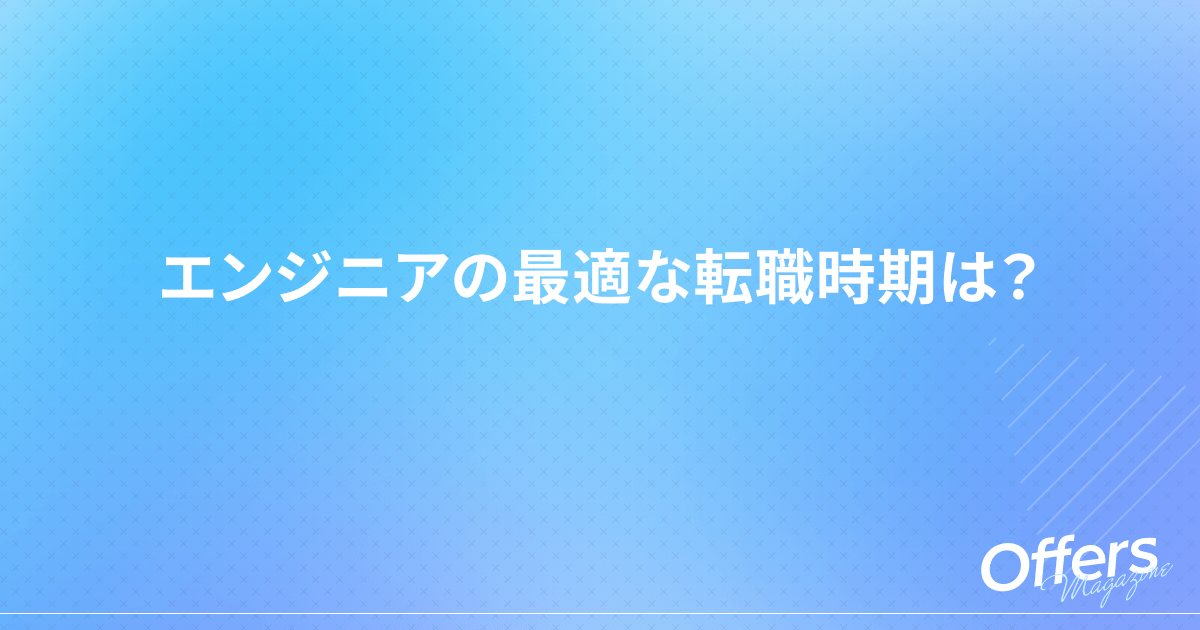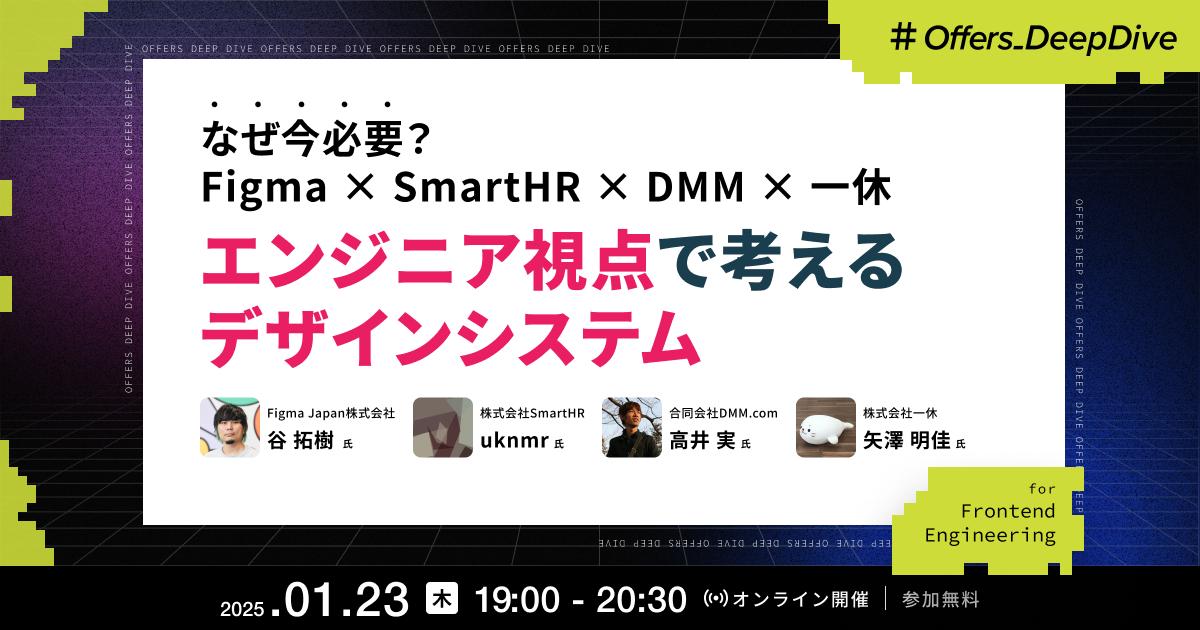エンジニアが転職を考えるべきタイミング
あなた自身のキャリアや働く環境への違和感を感じるとき、それは転職を考える重要なサインかもしれません。ここでは、ミドル層のWebエンジニアに特に多い“転職すべき局面”を整理しました。自分の状況と照らし合わせてチェックしてみてください。
成長が感じられなくなったとき
技術的な伸び悩みやルーチンワークの繰り返しに閉塞感を覚えたら、キャリアの節目に来ている可能性があります。「最近、新しいことを学べていない」「同じような作業ばかりで刺激がない」――そんな停滞感があるなら、転職によって環境を変えることで再び学びや成長の機会を得られるかもしれません。
特に30代以降は「この数年で何を積み上げるか」がキャリア全体に影響を及ぼします。現職で得られるものが尽きたと感じたら、新しい挑戦を選ぶ価値は十分にあります。
新しい技術・領域に挑戦したくなったとき
「クラウドに本格的に携わりたい」「AI・データ基盤に関わるプロジェクトに参加したい」など、明確に扱いたい技術があるのに、今の職場ではその機会が得られない——。それは転職を前向きに考えるべきシグナルです。
Webエンジニア業界は技術革新のサイクルが速く、今学びたい技術を逃すと数年後には“実務未経験”として取り残されることも。
「いつかやりたい」ではなく、「今動く」ことがキャリア形成を加速させます。
企業文化や働き方に違和感を感じたとき
会社の文化や働き方に違和感が募ってきたら、それも転職を検討するサインです。
たとえば「リモートに消極的で柔軟性がない」「エンジニア軽視の風土がある」「成果より年功が評価される」など、日々のストレスが積もる環境では、どんなにスキルがあっても力を発揮できません。
特にキャリア中盤では、自分なりの働き方や価値観が固まり始めるタイミングでもあります。
今の会社でそれを実現できないなら、“カルチャーフィット”する職場を探す行動は決して後ろ向きではなく、自分らしいキャリアを築くための前向きな選択です。
評価や待遇に不満を抱いたとき
「成果を出しているのに評価されない」「昇給が頭打ちになっている」
このように評価制度や報酬への不満は、多くのエンジニアが転職を考えるきっかけとなっています。
特に5年以上同じ会社にいると、昇進ポストが埋まっていたり、待遇が横ばいになったりすることが珍しくありません。
市場価値に対して社内評価が見合っていないと感じたら、転職によって待遇を見直すことも選択肢の一つです。実力に対して正当に報いられる環境は、やりがいや自己肯定感にも直結します。
転職を意識する“個人的なきっかけ”にも注目を
一方で、「明確なキャリア課題」だけでなく、私生活の変化をきっかけに転職を考えるケースもあります。特に以下のようなライフステージの変化は、働き方を見直す大きな契機になります。
ライフステージの変化(結婚・出産・引っ越しなど)
結婚や出産、育児、介護といったライフイベントの変化は、働き方を見直す大きな契機になります。実際に「結婚や出産を機に転職を考える」というケースは珍しくありません。
家庭との両立が難しくなれば、より柔軟な勤務形態や残業の少ない職場を求めて転職するのは前向きな選択肢と言えるでしょう。
ただしライフステージ真っ只中での転職では、「勤務地や勤務時間など絶対に譲れない条件」にとらわれがちです。
もちろん条件面の優先は大切ですが、例えば育児や介護が一段落した後にキャリアを再加速させたい場合は、将来に描く姿とのバランスも考えておくことが重要です。
ライフイベントに伴う転職では、短期的な働きやすさと中長期的なキャリア形成の両面からタイミングを判断しましょう。
キャリアステージにおける悩み
キャリアのステージに応じて、悩むポイントも変わってきます。以下は、「ジュニア・ミドル・シニア」の3つのステージそれぞれの悩みや環境についてまとめました。
キャリアステージにおける悩みと選ぶべき環境
| フェーズ | 主な年次目安 | よくある悩み・課題 | 選ぶべき/選ばれている環境 |
|---|---|---|---|
| ジュニア | 1〜3年目程度 | ・スキルの方向性が定まらず、どの領域に注力すれば良いか分からない
・経験不足でやりたいタスクを任せてもらえない ・業務キャッチアップに追われ設計やノウハウが身につかない |
・メンターやOJT制度が充実している企業(コードレビュー・学習サポートあり)
・幅広い業務に挑戦できる小規模チームや新規事業部 ・研修・スキルアップ支援制度が整っている環境 |
| ミドル | 3〜9年目程度 | ・技術を極めるかマネジメントに進むか悩む
・上流工程(要件定義・設計)に関わりたいが機会が少ない ・チーム運営や後輩指導などのコミュニケーション負荷に戸惑う |
・TL/PMロールや上流工程に関われる機会がある企業
・専門領域を深掘りできるプロジェクトが豊富(例:AI、SRE、セキュリティなど) ・リーダー経験を積めるポジション(少数精鋭やスタートアップなど) |
| シニア | 10年目〜リード級 | ・コーディングから離れ、最新技術に触れられないことへの不安
・意思決定や調整の難しさに直面 ・自分のエンジニアリングが時代に合っているか不安 |
・マネジメントと技術の両面に関われるポジション(CTO直下など)
・複数プロジェクトを俯瞰し、新技術導入や大規模リファクタに挑戦できる環境 ・長期的視点で組織成長に関われる企業(知見を活かせる) |
それぞれのキャリアステージにおいて直面する課題は異なり、転職の動機や目的も変化します。
大切なのは、「今の自分の悩みがどのステージ特有のものか」を客観的に把握し、その悩みを解消できる環境へと一歩踏み出すことです。
市場の動向(IT業界の求人動向・企業の採用ニーズ)
景気や業界動向によって、採用市場の熱度も変化します。ITエンジニアの求人市場は近年ずっと活況で、厚労省のデータによれば、令和5年度における情報処理・通信技術者の求人倍率は7.0倍です。
つまり「1人のエンジニアを7社が奪い合う」状態であり、エンジニアにとって売り手市場と言えます。
求人倍率が高く企業の採用意欲が強いタイミングでは、内定を獲得しやすいだけでなく提示される年収も上がりやすい傾向があるため、転職としては良いタイミングと言えるでしょう。
今後は少子高齢化が進み、さらにIT人材の不足が懸念されることから、より良い条件で転職できる可能性は高まります。
その一方で、エンジニアの求人倍率が職種や分野によって下がるという懸念もあります。
それは、AIの台頭によって代替可能なエンジニアの業務です。具体的には、テストコードの生成やCRUD処理(Create/Read/Update/Delete)のような繰り返し構造のある実装、既存コードのリファクタリング提案は、現時点でもAIの方が遙かにパフォーマンスが高い領域です。

これらの仕事をメインにしている場合、エンジニアとしての価値が時間とともに下がる可能性は否定できません。逆に意思決定やチームマネジメントといった上流工程は長く人間に求められるスキルであるため、早期に上流工程の経験が詰める環境が求められます。
このように、将来にわたる市場の動向を把握し、「転職しやすい時期はいつか?」を見極めることも大切です。
また、自社が属する業界のトレンドや新技術の波も意識しましょう。たとえば新たな技術スタックが主流になり、自社でそれに触れられない場合、市場価値を高めるため転職を考えることも一つの戦略です。
例えば、以下のグラフはOffersに登録しているエンジニアが保有しているスキルの成長率です。(右上)

AIのトレンドもあり、Pythonが上位、また、成長率ではNode.jsが急速に伸びていることがわかります。企業側の技術スタックは遅れて転換してくるため、今から次世代のスキルを習得しておくことで市場価値を高めることができるでしょう。
キャリアプランの再検討(スキルアップ・マネジメント志向・年収アップ)
キャリアプラン上の理由で転職を考えるエンジニアも多くいます。例えば「このままでは自分のスキルが伸びない」「マネジメントに挑戦したいが今の会社ではポジションが限られる」「成果を出しているのに給与が見合わない」といった不満です。大企業で部分的な業務しか任されずやりがいを感じられなかったり、扱う技術が古くこの先の成長に不安を感じたりすれば、スキルアップのための転職を検討するのは自然な流れでしょう。
また20代後半から30代前半は「将来どの道に進むか」を定め始める時期です。現場志向で専門スキルを極めるのか、マネジメントや企画側にシフトするのか、あるいは起業やフリーランスなど別の道か──このキャリアの岐路に立ったとき、新たな環境を求めることがあります。
「5年後・10年後にどうありたいか」を描き、それに現在地が合っていないと感じたなら、転職という選択肢が浮上するでしょう。いずれにせよ、自分のキャリア目標を明確にした上で転職活動を始めることが成功への第一歩です。
スキル観点
Offersが提供しているSkill Treeではエンジニアのスキル習得のロードマップを可視化することで、自身のスキルアップの道筋をつくるサポートをしています。
現職で何を得たいか、もしくは転職先では得たいスキルが得られるのか、といった観点で自身のキャリアプランを再検討してみることをおすすめしています。
Offersでは無料でキャリアの壁打ちができますので、より詳しいお話はお気軽にこちらからご登録ください。

転職に最適な時期
次に、「いつ転職するのが良いか」という時期的な観点を見ていきます。
年間を通じて求人が増えるシーズンや、退職・入社に適したタイミングがあります。ここでは一般的に言われる転職市場が活発になる時期と、ボーナスやプロジェクト区切りといったポイントをご紹介します。
年間で求人数が増える時期を狙う
1年のうちで、どの時期が転職に適しているかを考えることも重要です。エンジニア採用における、転職に適した時期を紹介します。
求人が増加するのは2~3月と8~9月
エンジニアの中途採用市場では、毎年2~3月と8~9月頃に求人が増加する傾向があります。
企業が上期・下期の始まりに合わせて人員を補強しようとするためで、この時期は募集ポジションも幅広く、普段はあまり求人が出ないような職種や部署の募集が見つかることもあります。
選択肢が増える分、求職者にとっては応募の好機と言えるでしょう。
ただしライバルも同様に増えるため、応募・面談の準備を万全にして強い意志で臨むことが大切です。
賞与(ボーナス)支給時期
賞与(ボーナス)支給時期も多くの人が転職を考えるタイミングです。一般的に夏(6月~7月)と冬(12月~1月)に賞与が支給される企業が多く、「ボーナスをもらってから辞めよう」と考える人が少なくありません。そのため例年、6~7月および11~1月頃は退職者が増える分、企業側も欠員補充の求人を活発化させる傾向があります。
実際、賞与支給前後のこれらの時期は求人数が増加する傾向にあり、企業も人材流出を見越して採用を強化することが要因となっています。
したがって「ボーナスをもらってから転職したい」という場合、その直後のタイミングで多くの求人に出会える可能性が高いでしょう。
入社したい企業がある場合は採用情報の随時チェックも重要
年度の切り替わりに向けて求人が増える時期を狙うのは一つの戦略ですが、一方で中途採用は欠員補充が中心のため「毎年○月に必ず募集が出る」とは限らない点にも注意が必要です。
入社したい企業や就業したい仕事がある程度決まっているなら、企業を絞り込んだ上で、定期的に求人情報をチェックすることをおすすめします。
プロジェクトの区切りを意識する
エンジニアであれば、担当しているプロジェクトの節目も転職のタイミングに影響します。
プロジェクトが佳境にある中での退職は、職場に迷惑をかけ自分も気まずい思いをしかねません。
理想的には、プロジェクトのリリース直後や運用フェーズに移行して落ち着いた段階など、比較的安定した時期に辞めるのが望ましいでしょう。
特にリーダーやサブリーダーの立場にいる場合は、後任となる人材を育成し、自分の役割を引き継げる状態を作ってから退職することが円満退社のポイントです。
法律上は退職の意思表示は2週間前でも可能とされていますが、現場の慣習として1ヶ月半~2ヶ月前までに申し出るのが一般的です。
長めの引継ぎ期間を設け、関係者への影響を最小限に留めれば、退職後も良好な人間関係を保ちやすくなります。
エンジニア同士の世界は広いようで狭いもの。プロジェクトの区切りを見極めて綺麗に去ることは、将来どこかで縁が繋がった際の自分の評判にも関わります。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、タイミングを図りましょう。
Offersではよりスピーディーな転職事例多数
一般に、転職活動開始から内定獲得までは平均2~3ヶ月程度かかると言われます。さらに現職の退職交渉や引継ぎに1ヶ月前後、加えて有給消化なども考慮すると、トータルで3~4ヶ月以上を見積もるのが無難です。
それよりもスピーディーに転職したい場合、Offesを活用してみてください。
Offersでは、わずか1カ月程度でスピーディーに転職成功を収めた事例が多数あります。
わずか1カ月で5名を採用!wizOnChainがドメイン知識と技術を兼ね備えた「スペシャリスト型チーム」を最短で組成できた理由とは
翌月には稼働開始!シニア層のAIやバックエンド/フロント、PdMのピンポイント採用に成功
もちろん、ただスピーディーなだけではありません。年収アップや転職後の満足度など、Offersを使った多くのエンジニアが「転職に成功した」と実感しています。
転職を成功させるポイント
タイミングを見極めたら、次は転職活動自体を成功に導くためのポイントを押さえましょう。情報収集の徹底、転職理由と目標の明確化、そしてエージェントやリファラル(社員紹介)活用の3つが重要です。それぞれ解説します。
徹底した情報収集と企業研究
転職成功の第一歩は、なんといっても情報収集です。自分に合った求人や企業を見つけるには、できるだけ多くの情報源に当たりましょう。
そして志望企業がある程度絞れてきたら、公式サイトの採用ページ、テックブログ、IR情報、開発者向けインタビューなどを確認しましょう。
企業の価値観・ビジョン・組織体制に加えて、具体的な技術スタックや開発スタイルも知ることができます。
さらにQiitaやZennでエンジニアが公開している記事を読むと、その会社の技術への向き合い方やナレッジ共有文化が見えてきます。
可能であればカジュアル面談や社内勉強会・ミートアップなどに参加し、現場の空気を肌で感じるのも有効です。
転職理由の整理とキャリア目標の明確化
十分な情報収集と並行して、自分の転職理由や目的を明確にしておく作業が欠かせません。
以下の点を明確化しておきましょう。
動機の言語化
なぜ転職したいのか、転職によって何を実現したいのかを言語化しておくことで、志望企業の選定や面接でのアピールに一貫性が生まれます。
漠然と不安だからといってタイミングだけ考えて転職しても、また同じ不安を抱えかねません。まずは自分がどんな働き方・仕事を望むのか考えることが大切です。
本質的な課題と目標をクリアにする
具体的には、現職で不満に思っている点(例:待遇、人間関係、成長機会、企業文化など)を書き出し、「それを転職でどう解決したいか」「次の職場で叶えたいことは何か」を整理しましょう。
また同時に、自分の強み・スキルや仕事への姿勢も振り返って棚卸しします。転職理由がポジティブに整理できると、企業選びの軸が定まり、複数のオファーで悩んだ際にも判断基準になります。
転職の目的がはっきりしていれば「条件の良さだけで飛びついて後悔…」といったミスマッチを防ぎ、内定獲得後に冷静に比較検討してベストな選択がしやすくなるでしょう。転職エージェント・リファラルの賢い活用
転職活動では、自力の情報収集・応募に加えて転職エージェントやリファラル(社員紹介)といった外部リソースも積極的に活用しましょう。
エージェントは非公開求人の紹介や応募書類の添削、面接日程の調整や年収交渉など幅広くサポートしてくれる心強い存在です。
特に多忙なエンジニアにとって、エージェント経由で効率よく求人紹介を受けられるメリットは大きいでしょう。
早めに信頼できるエージェントに登録し、市場の最新動向を定期的に教えてもらうのがおすすめです。「良い求人があれば話を聞きたい」というスタンスでも構いませんので、在職中からエージェント経由で情報収集しておくとチャンスを逃しにくいでしょう。
一方で、前述のリファラル採用(社員や知人からの紹介)も可能なら是非活用したいところです。知人の紹介は高い確率でミスマッチの少ない転職を実現できる方法ですが、常に都合良く話があるとは限りません。
日頃からエンジニアコミュニティの交流を増やし「良い人いたら声かけてね」と伝えておくなど、長期的なネットワーキングも大事です。最近では社員紹介制度を整える企業も増えており、紹介経由の応募者にはカジュアル面談の機会を設けたり選考を優遇したりするケースもあります。
身近に目指す企業で働く知人がいないか、SNS等でそれとなく情報収集してみるのも良いでしょう。
転職のために準備すべきこと
転職のタイミングと戦略が固まったら、実際の選考対策に向けた準備を入念に行いましょう。
ポートフォリオやGitHubの整理
Web系エンジニアの転職では、実績やスキルを客観的に示す資料があると強力な武器になります。
具体的には、これまで携わったプロジェクトの成果物をまとめたポートフォリオサイトや、GitHub上のリポジトリ、技術ブログ・Qiita記事などがそれに当たります。
特にGitHubやQiitaでのアウトプットは、面接官があなたの技術スタックやコードの書き方、課題解決能力などを知る手がかりになります。
またQiitaやZennに投稿している場合は、現場で学んだ知見や問題解決のプロセスが分かる記事があると、「どういう観点で開発に取り組む人か」「学習意欲は高いか」を評価者に伝える材料になります。
自分のGitHubが古いまま放置されていたり、ポートフォリオに更新がない状態だと少々もったいないので、転職活動開始前に最新の情報にアップデートしておくことをおすすめします。
STAR形式で実績をまとめる
面接前にSTAR形式で実績をまとめることで、面接官に自身の経験やスキルを効果的に伝えることができます。

面接対策(技術・カルチャーフィット)
エンジニアの中途採用面接では、技術力の見極めとカルチャーフィットのチェックが重視されます。それぞれ対策のポイントを押さえておきましょう。
技術選考対策
エンジニアの転職においては、技術選考は必ず行われます。また、技術選考が落ちる確率が最も高い選考とも言われています。万全の対策をして、準備に望みましょう。
以下の表は技術選考の種類と、それらの特徴や難易度をまとめたものです。

技術面接対策
職務経歴書やポートフォリオに沿って、具体的な技術的取り組みを説明できるよう準備します。
自分の書いたコードや設計上の工夫について聞かれても対応できるようにしておきましょう。
必要に応じて、代表的な成果物のコードを読み返したり、システムアーキテクチャを図解して説明練習しておくと安心です。
また企業によってはコーディングテストやアルゴリズム問題、設計課題などを出すこともあります。普段触れていない分野であれば事前に復習し、LeetCodeやAtCoder的な問題演習をしておくのも一手です。
カルチャーフィット面接対策
技術力が十分でも、企業文化やチームとの相性が合わなければ長く活躍するのは難しいものです。
面接ではあなたの人柄や働き方のスタンスも見られています。企業研究で掴んだ社風に照らし合わせて、共感できるポイント(例:「ユーザーファーストの開発理念に惹かれた」「学習促進の社風で成長できそう」など)を自分の言葉で伝えられるように準備しましょう。
逆に前職の愚痴や不満ばかり語るのはNGです。退職理由を聞かれた際は、ネガティブな動機そのままではなく「こういう環境で〇〇に挑戦したい」という前向きな展望に言い換えて答えると好印象です。
最後に、基本的なことですがスケジュール調整やレスポンスの速さも評価に影響します。
多忙な中でも面接日程の提案に迅速に返答し、面接当日は5分前にはオンライン待機または会場到着しておくなど、社会人としての信頼感を損なわないよう注意しましょう。
転職タイミングと本当に転職していいかチェックするポイント
ここまで転職のタイミングや成功のコツについて述べてきましたが、最後に「本当に今転職すべきか」を冷静に見極める視点について触れておきます。
勢いで転職して後悔しないために、以下のポイントをチェックしましょう。
現職に残る選択肢も含め比較検討する
転職を考えるとき、つい「辞める」前提で物事を進めがちですが、一歩立ち止まって現職に留まる道も検討してみてください。
実は、転職市場を調べたり他社の話を聞いた上で「やはり今の会社に残ろう」と判断するのも立派な成果です。
周囲が転職しているから自分も…と焦る必要はありません。
現職で解決できる課題(部署異動や待遇交渉等)があるならまず模索してみるのも手ですし、タイミングをずらせばより好条件のオファーが得られる可能性もあります。
「本当にいまこのタイミングで辞める必要があるのか?」を自問し、現職に残った場合のメリット・デメリットも含めて総合的に比較検討しましょう。
転職はあくまで手段であって目的ではありません。自分のキャリア充実という目的に照らし、ベストな選択は何かを冷静に判断してください。感情的な判断を避け、冷静になる期間を持つ
人間関係のもつれや上司への不満、ハードワークによる疲弊などで「もう辞めたい!」と感情が爆発しそうになることもあるでしょう。
しかし感情が高ぶった状態での転職決断は危険です。一時的な怒りや不安で衝動的に退職してしまうと、あとで冷静になったとき「もう少し頑張れたかも」「他に道があったかも」と後悔するケースも少なくありません。
そうした事態を防ぐために、心が揺れた時こそ少し時間を置いてクールダウンすることが大切です。
例えば「もう辞める!」と思ってもすぐには行動に移さず、数日~1週間考えてみる、信頼できる同僚や第三者に愚痴ではなく相談として話してみる、などです。
キャリアアドバイザーに相談してみるのも有効でしょう。勢い任せの退職は避け、落ち着いて意思決定できる精神状態を整えましょう。
中長期的キャリア設計の視点で判断する
最後に、転職のタイミングを判断する際には中長期的なキャリア設計の視点を忘れないようにしましょう。
目先の年収アップや人間関係リセットだけにとらわれず、「この転職は5年後、10年後の自分にどうプラスになるか?」という観点で考えることが重要です。
キャリアの多様化が進む現代では、必ずしも全員が管理職を目指す必要はなく、専門性を極めてスペシャリストになる道や、ワークライフバランス重視で柔軟な働き方ができる会社に移る道など様々な選択肢があります。
自分が望む将来像を描き、その実現に近づくステップとして今の転職が適切かどうか検討しましょう。「転職後に何を成し遂げたいか」「どんな成長を遂げたいか」を具体的にイメージできるなら、そのタイミングは適切だと言えます。一方で将来像がぼんやりしたままだと、転職して環境が変わっても再び悩む可能性があります。
転職はゴールではなく新たなスタートです。中長期的なキャリアプランの中で今このタイミングがベストなのか、改めてチェックしてみてください。
最後にもう一度、自問してみましょう。
「今このタイミングの転職は、自分の人生にとってベストな一手と言えるか?」
その答えがYESであれば、あとは勇気を持って一歩踏み出すのみです。あなたの転職が実り多いものとなることを願っています。